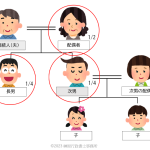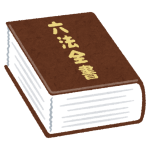当サイトの一部にアフィリエイト広告を含みます。
相続が発生した際、遺産分割がスムーズに進まないことはよくあります。その中でも、最も深刻な問題の一つに「相続人による遺産の使い込み」があります。一部の相続人による遺産の使い込みは、相続人同士の感情的な対立を招くおそれがあります。しかし、そんなときこそ冷静に対応し、適切な手続きを踏むのが最適解です。
この記事では、遺産を不正に使い込んでいる相続人への具体的な対処法を解説します。法的な手段から、家庭内で解決できる方法まで、どのように進めるべきかを詳しくご紹介しますので、同じような問題に直面した際には参考にしてください。
遺産の使い込みに気づいたら最初にするべきこと
遺産の使い込みに気づいた場合の対処法として、以下の方法が考えられます。
1.証拠を集める
遺産の使い込みに関する証拠は、しっかりと集めましょう。仮に証拠がない場合、後に法廷で争う場合に不利になるケースが多いことから、証拠収集は慎重に行う必要があります。証拠として有効なものとして、以下が考えられます。
- 銀行の取引履歴
- 領収書、支払い明細
- 第三者の証言
相続人との話し合い
一部の相続人が遺産を使い込んでいることが発覚した場合、冷静かつ建設的な話し合いができると理想です。感情的になるのは当然ですが、問題を解決するには相手との対話が不可欠です。誤解や不安から不正行為に及んでいる可能性もあり得るため、話し合いを通じて誤解を解き、問題の本質を把握するよう努めましょう。
話し合いの際は、できる限り穏やかに、落ち着いた口調で伝えるのがポイントです。相手を責めたり決めつける言い方、感情的な発言は避け、冷静に状況を説明し、一緒に解決策を考える姿勢を示すのがベターだといえます。
話し合いのポイント
①冷静な言葉で伝える
主語を「あなた」にするのではなく、「わたし」にするとスムーズに運ぶことがあります。たとえば、「私は、遺産の使い道について疑問を抱いている」という言い回しにすることで、相手を非難する姿勢を回避することができます。
②誠実な対応を心がける
相手に対し、遺産を使い込んでいることを指摘するだけでは反発されるおそれがあります。相手の行動についてどのような理由があるのかを知るため、まずは傾聴の姿勢を取りましょう。たとえば、「何か困ったことがあったの?」、「遺産をどのようなことに使ったの?」と質問し、相手の意図を理解するよう努めましょう。
③解決策を一緒に考える
遺産の使い込みについて、相手からの説明を受け、誤解が生じていた場合には今後の対応を一緒に考える必要があります。「これからのことを一緒に話し合いたい」「遺産の分け方について、改めて考えていこう」と前向きに運ぶことで、対話がスムーズになる可能性が高まります。
④感情的な反応は避ける
遺産を使い込んだ相手が自分の行動を正当化しようとしたり、否定的な反応を示すこともありますが、こちらまで感情的に反応するのは賢明とはいえません。できる限り冷静さを保ち、対話を続けましょう。一度の話し合いで解決に至ることは稀ですので、気長にどっしり構えると○です。
話し合いが進まない場合
相手が意図的に不正を行っている場合や、話し合いに応じてくれない場合、話し合いが硬直化している場合には、法的な手段を講じることとなりますが、そうなると精神的にもつらくなります。ですので、できる限り話し合いで解決を目指すのが理想的だといえます。
遺産分割協議を求める
使い込まれた遺産について、相手の法定相続分以下であれば遺産分割協議にて調整することができます。一方、法定相続分を超えている場合には、超えた部分を返還するよう求めることになります。
この際、後にトラブルに発展しないよう合意書、または公正証書を作成しておくと安心です。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議を進める際は、以下に注意しましょう。
①冷静に進める
繰り返しになりますが、使い込みに対し憤りを感じる方が多いのも理解できますが、その後を考え、できる限り冷静に対処しましょう。遺産分割協議の目的は、問題を解決し、相続人全員が納得できる落としどころを見つけることです。そのため、感情的な発言や攻撃的な態度は控え、慎重に臨みましょう。
②使い込み金額を明確にする
遺産の使い込みについて、集めた証拠を基に、どの遺産が、どのくらい使われたのかを明確にしましょう。
③公平に分ける方法について話し合う
使い込まれた遺産の取り扱いについて話し合いましょう。たとえば、使い込んだ相続人がその価額を補填する形で他の相続人に譲歩を求めたり、使い込んだ価額を差し引いて遺産を分割する方法も考えられます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要なことから、すべての相続人が納得できる方法を見つけていきましょう。
④弁護士の助言を受ける
遺産分割協議が滞る場合や、一部の相続人が話し合いに応じない場合、弁護士に助けを求める選択肢もあります。弁護士に依頼すると、相続人同士で直接顔を合わせる必要がありませんし、裁判に比べ、早期の解決が期待できるほか、万が一裁判で争うことになったとしても引き続き対応を任せられるメリットがあります。
⑤調停、審判を視野に
当事者間での話し合いが難しい場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停では、調停委員会を介して話し合いを重ねながら解決を目指します。合意に至らなかった場合には審判へと進み、最終的に裁判所の判断に委ねることになります。
遺産分割協議の内容を実施
遺産分割協議が調った場合には、遺産分割協議書を作成し、合意に至った内容を遂行することになります。
法的手段を検討する
一部の相続人による遺産の使い込みが明らかになった場合、当事者間での話し合いだけでは解決できないこともあります。この場合、法的な手段を検討することとなります。
遺産分割調停の申立て
遺産分割調停とは、裁判官と調停委員とで構成される調停委員会を介し、話し合いによる解決を目指す制度です。
①申立人
遺産分割調停の申立てができるのは、原則、相続人です。具体的には、以下の通りです。
- 共同相続人
- 包括受遺者
- 相続分譲受人
②申立ての条件
遺産の使い込みについて、使い込みを疑われる一部の相続人を除き、相続人全員の合意が必要となります。
③申立先
遺産分割調停の申立て先は、相手方となる相続人のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者の合意により決定した家庭裁判所のいずれかです。
【関連リンク】裁判所の管轄区域(裁判所)
④費用
遺産分割調停を申立てるには、故人一人につき収入印紙1200円分+連絡用の郵便切手代が必要です。ただし、郵便切手の金額や組み合わせは申立先となる家庭裁判所により必要数が異なるため、事前に確認しましょう。
【関連リンク】各地の裁判所一覧(裁判所)
⑤申立てに必要な書類
申立てに必要な書類は、以下の通りです。
| 書類名 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|
| 申立書 | 申立書1通およびその写しを相手方の人数分 | 書式/記載例 |
| 共通 | 故人の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | ー |
| 相続人全員の戸籍謄本 | ||
| 故人の子(及び代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合 その子の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | ||
| 相続人全員の住民票、または戸籍附票 | ||
| 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書および固定資産評価証明書/預貯金通帳の写し、または残高証明書/有価証券の写し など) | ||
| 相続人が直系尊属の場合 (父母、祖父母など) | 故人の直系尊属に死亡している方がいらっしゃる場合 その直系尊属の死亡記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | |
| 相続人が配偶者のみの場合、または第三位相続人の場合 (配偶者+兄弟姉妹) | 故人の父母の出生時から死亡までの連続する戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | |
| 故人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | ||
| 故人の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合 その兄弟姉妹の出生から死亡までの連続する戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | ||
| 代襲者の場合 (おい、めい) | 代襲者としての「おい、めい」に死亡している方がいらっしゃる場合 そのおい、またはめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
家庭裁判所の遺産分割手続きは、遺産を探し出すことを目的とするものではありませんが、調停に際し、その遺産の範囲や内容について意見を聴き、必要資料の提出を促すことはあります。
その際、ほかにも遺産があると考えられる場合には、原則、その裏付けとなる資料をご自身で提出しなければならず、ここで集めた証拠が火を噴きます🔥
不当利得返還請求を行う
不当利得返還請求とは、他人の権利を侵害して得た利益を返還するよう求めるものをいいます。遺産の使い込みについて言えば、生前の使い込みや、使い込んだ金額が遺産総額の大半を占める場合に有効な手段です。
不当利得返還請求を行うためにクリアすべき要件
不当利得返還請求を行うには、以下の要件をクリアしなければなりません(民法第703条)
- 他人の財産を不法に得たこと
- 返還請求することに利益があること
- 利益返還について法的な根拠があること
たとえば、遺産の一部である現金や預貯金について、遺産分割協議が終わる前に相続人Aさんが無断で引き出し、生活費や個人的な支出に使ってしまった場合。遺産を使い込まれた他の相続人は、不当利得返還請求を行うことができます。
なぜなら、Aさんが無断で使い込んだ現金や預貯金は、他の相続人の権利を侵害して不正に利益を得たものであり、正当な権利者に返還すべきだと考えられるからです。
不当利得返還請求の時効
不当利得返還請求を行うには、使い込みのときから10年、または使い込みを知ったときから5年という期限があります。ですので、この期限内に請求を行う必要があります。
【関連記事】不当利得返還請求の流れ、注意点を解説
不法行為に基づく損害賠償請求を行う
遺産の使い込みは、不法行為に基づく損害賠償の請求対象にもなります。
不法行為に基づく損害賠償請求とは、他人の権利を侵害する行為があった場合に、その侵害により被った損害を補填するため、加害者に対し損害賠償を求めることをいいます(民法第709条)。
不法行為に基づく損害賠償請求を行うためにクリアすべき要件
不法行為に基づく損害賠償請求を行うには、以下の要件をクリアしなければなりません。
- 加害者の行為が不法であること
- 加害者の行為により損害が生じた事
- 損害と加害行為とのあいだに因果関係があること
不法行為による損害賠償の種類
不法行為による損害賠償の種類は、以下に分けられます。
| 物的損害賠償 | 物理的な損害が対象 |
| 精神的損害(慰謝料) | 身体的な損害や名誉棄損などにより精神的な苦痛を被った場合、慰謝料が支払われることがあります |
| 逸失利益 | 不法行為により被害者が得られたはずの利益を損失として賠償するものです |
請求する損害の種類がどれに該当するか冷静に見極め、適切に対処する必要があります。
弁護士に相談する
遺産の使い込みに気づいた場合、感情的に反応したり、自己判断の実で進めるのは事態悪化のリスクを伴います。相続問題は非常に複雑ですので、弁護士への相談をお勧めします。弁護士への相談をお勧めする理由は、以下の通りです。
- 専門的な知見が期待できる
- 具体的な手段についてアドバイスを受けられる
- 冷静な対応を促してくれる
①専門的な知見が期待できる
弁護士は、相続だけでなく法律の知識を網羅的に習得しており、遺産分割協議や不法利得返還請求、不法行為による損害賠償などの手続きについてもご存じです。適切な対応ができなければ後に大きなトラブルに発展することもありますので、早期に相談することで、将来的なリスク回避につなげることができます。
②具体的な手段についてアドバイスを受けられる
遺産の使い込みに対し法的手段に訴え出る場合、その手続きをどのように進めるか弁護士はガイドしてくれます。第三者が介入することにより当事者も冷静になることができ、民事訴訟を提起する前に交渉で解決できることもあります。
③冷静な対応を促してくれる
相続問題は当事者が感情的になりやすく、判断を誤るケースも少なくありません。この点、弁護士は客観的に問題を把握、分析し、最適解を提案してくれますので、感情に流されず当事者が納得できる答えを導き出せる可能性が高いといえます。
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談を検討する際は、以下のタイミングがお勧めです。
- 遺産の使い込みに気づいた段階
- 遺産分割協議が難航したとき
- 法的な手段を検討するタイミング
弁護士への相談に必要な情報
弁護士に相談する際は、以下の情報を揃えておくとスムーズです。
①遺産に関する資料
遺産の内容、相続人の情報、相続人同士で行った遺産分割協議の内容など、遺産に関する詳細な資料を準備しておくと安心です。また、使い込みに関する証拠を整理しておくと更にスムーズな対応が期待できます。
②遺産の使い込みに関する資料
遺産のうち、使い込まれた財産の種類、金額、使途について、できる限り証拠を集めておきましょう。弁護士に証拠を提示することで、さらに詳細なアドバイスが期待できます。
③相続人の意向と教義の進捗
相続人の間で遺産分割協議がどのように進められ、どういった問題で対立しているのかを弁護士に伝えられると○です。これは、必ずしもわからなくても構いませんが、ご自身がどうしたいのかというゴールがわからなければ、弁護士もアドバイスの仕様がありません。
遺産の使い込みに関する事例
ここからは、実際の事例を用いてみていきます。
事例1: 相続人が遺産の一部を無断で使用
お父様が亡くなり、遺産が相続されることになりました。相続人は3人のご兄弟で、遺産には不動産と預金が含まれています。遺産分割協議が行われる前に、長男がお父様の預金口座から数百万円を無断で引き出して使ってしまいました。
問題点
この事例では、長男が他の相続人に無断でお父様の預金を引き出し、生活費や個人的な支出に使ってしまっています。これに対し、次男と三男は「不公平だ!」と主張し、遺産分割協議において問題となりました。
対処方法
次男、三男がとれる対処法として、まずは当事者間での話し合いと証拠集めが考えられます。これらが難航しますと、調停や不当利得返還請求、不法行為による損害賠償を考えることになるでしょう。いずれにせよ、証拠として銀行の取引履歴を提出し、不正に引き出された金額を証明する必要があります。
この件では、調停や訴訟に発展する前に、長男が使い込んだ金額を二人に返還することで合意に至り、遺産分割協議が再開されました。
事例2: 相続人が遺産を事前に使用
お母様が亡くなり、相続人は2人のお子さん(AさんとBさん)、遺産は現金や不動産がある事例です。遺産分割協議が始まる前において、Aさんはお母様名義の預金口座から全額を引き出し、自分の事業資金に充てました。
問題点
Aさんは、お母様が亡くなった後において、ご自身が相続する予定の金額を無断で使いました。遺産分割協議が始まった後にこれが発覚し、更なる使い込みを疑うBさんとの間で協議が難航しています。
対処方法
当事者間での話し合いが難しいことから、弁護士への相談や、家庭裁判所への申立てが考えられます。
Bさんの場合、弁護士への相談を選択し、Aさんへの法的措置を決意され、不当利得返還請求を実行。最終的に、Aさんは自らが使い込んだ金額を賠償する形で決着がつきました。
事例3: 親の財産を個人的に使った相続人
Cさんのお母様が亡くなり、遺産には、不動産、現金、株式などが含まれています。お母親の生前より、Cさんは自らの生活費をお母様名義の口座から引き出していましたが、死後も同様に引き出し、結果的に遺産の一部を使い込むこととなりました。
問題点
遺産分割協議において、Cさんは遺産の使い込みを認めませんでした。これに対し、他の兄弟姉妹から不満の声があがり、遺産分割協議が滞っています。
対処方法
兄弟姉妹がとれる最初の対処法は、Cさんがお母様名義の預金や株式の配当金等を無断で使用した証拠を集めることです。遺産分割が停滞していることから、家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申立てを行うのが適切かと思われます。
実際にこの件では、調停を通して解決が図られ、Cさんは使い込んだ金額を返還することで決着となりました。
事例4: 相続人が不動産を売却し、利益を独占
お父様が亡くなり、遺産には、実家である「土地・家屋」が含まれています。配偶者に先立たれていたため、相続人はお子さん4人です。このうち、長男が無断で不動産を売却し、得た利益を独占している事例です。
問題点
長男が不動産を売却すること、売却して得た金額を他の子に一切開示せず、独占して使用してしまったことが問題となっています。これに反発した兄弟姉妹との間に確執が生じ、遺産分割協議は進まなくなってしまいました。
対処方法
長男以外のお子さんは、はじめに証拠を集める必要があります。具体的には、売却された不動産情報のほか、売却によって得た価額を調べることとなります。これらを基に不法利得返還請求を行い、法廷で争うことになるでしょう。
実際に彼らは訴訟を提起し、長男の不当利得が認められた結果、売却代金を他の相続人に賠償することとなりました。
事例5: 生前贈与と遺産の不正使用
お母様が亡くなり、遺産を分割することとなりました。この際、生前に贈与を受けていた長女がそのことを開示しないまま参加したのですが、後に発覚。相続人同士で争いが生じました。
問題点
長女は、お母様からの生前贈与について黙っており、他の相続人はそのことを知らず、また、自分たちは贈与を受けていないことを理由に混乱が生じています。
対処方法
長女以外の相続人は生前贈与の内容を確認し、遺産分割協議の中で調整する、または同額を返還するよう求めることができます。
この事例では、長女が自身の受け取った証拠を提出し、その金額を彼女の相続分から差し引く形で遺産分割協議が調うこととなりました。
おわりに
この記事では、遺産の使い込みに気づいた場合の対処法について、具体的な手続きや方法を解説しました。相続人が遺産を無断で使用することは、感情的な対立を引き起こしやすく、問題を放置すると長期的なトラブルに発展することがあります。しかし、冷静に証拠を集め、適切な法的手段を講じることで、解決へと導くことが可能です。
遺産分割協議を進める際や、法的手続きを取る際には、弁護士のサポートを受けることも一つの方法です。弁護士や税理士、司法書士、行政書士の手を借り、適切に進めることで、よりスムーズに問題解決が図れるかと思います。
相続に関する問題は感情的になりやすいですが、冷静な対応を心がけ、最適な解決策を見つけることが重要です。問題が複雑化する前に早めにご相談くださいね。