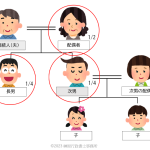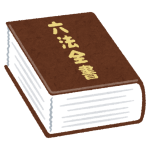当サイトの一部に広告を含みます。
遺産に投資信託が含まれる場合、その相続手続きは他の財産と同様に重要です。投資信託とは、多くの投資家が共同でお金を出し合い、その資金を運用会社が管理・運用する金融商品で、株式や債券、不動産など様々な資産に投資することができます。遺産の中に投資信託が含まれる場合、相続人はその取り扱いを慎重に決定する必要があります。
本記事では、投資信託の相続手続きについて、遺言書がある場合、遺産分割協議を行う場合、調停や審判を経る場合に分けて解説し、相続に伴う手続きや注意点について詳しくご紹介します。
【関連記事】相続の基本ステップ:遺産調査から承継手続きまでの流れ
Contents
投資信託とは
投資信託とは、多くの投資家が共同でお金を出し合い、その資金を運用の専門家である運用会社が管理・運用する金融商品をいいます。端的に言うと、投資信託とは「資金の運用をプロに任せる仕組み」だと言えます。具体的には、投資信託を通じ、個人が株式や債券、不動産など様々な資産に投資することができますが、直接その資産を購入するのではなく、運用会社が代わりに投資を行い、運用成果を信託に参加している投資家に分配します。
遺産の中に「投資信託」が含まれる場合、他の遺産と同じように相続手続きを行う必要があります。
投資信託を相続するために必要な手続
投資信託を相続するために必要な手続きについて、以下に分けて解説します。
- 遺言書がある場合
- 遺産分割協議を行う場合
- 調停・審判を行う場合
1.遺言書がある場合
故人が有効な遺言書を作成している場合、原則、遺言の内容に従って分割することになります。そのため、投資信託をどのように扱うよう指示されているのか、遺言書を確認する必要があります。以下は、一般的な例です。
- 投資信託をそのまま相続人に引き継ぐ(名義変更)
- 投資信託を売却し、売却代金を分割する
- 特定の相続人を指定し、投資信託を譲渡する
遺言書に上記のような指定がある場合、原則、その内容に従うことになります。
1.1. 遺言書の検認手続き
遺言書は、「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」に分けることができます。故人が作成したものが自筆証書遺言書だった場合、基本的には家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。
一方、公正証書遺言書だった場合、この手続きは必要ありません。
【関連記事】遺言書の検認手続が必要な場合、手続の流れを解説
2.遺産分割協議をする場合
遺産に投資信託がある場合において、遺言書がない、または遺言書の内容と異なる分割方法を希望する場合には、遺産分割協議を通じ、相続人全員でどのように投資信託を分けるかを決定し、手続きを進めることになります。この際、投資信託を現物のまま分けるのか、現金化してから分けるのかを決定することになります。
すべての相続人が合意に至ったら、合意した内容を遺産分割協議書にまとめ、全員が署名押印をする必要があります。
2.1.投資信託の分割方法
投資信託の分割は、以下のいずれかの方法によることとなります。
| 1 | 現物分割 | 投資信託をそのまま相続人ごとに分割する方法 |
| 2 | 代償分割 | 一部の相続人が投資信託をそのまま相続し、他の相続人にその価額に見合った現金や他の資産で代償を支払う方法 |
| 3 | 換価分割 | 投資信託を売却して得た代金で遺産を分割する方法 |
2.2. 遺産分割協議書を作成する際の注意点
遺産分割協議書を作成する際は、故人や相続人の氏名、続柄、生年月日、住所等を正確に記載しましょう。また、遺産の内訳において、投資信託は証券口座番号、金融機関名、評価額(評価方法)、銘柄など、具体的な情報を記載する必要があります。投資信託の分割方法についても、明確に記載しましょう。
投資信託の相続に伴い、相続税が発生する場合には、誰がどのように負担するかを記載しておくと後のトラブル防止につながります。
【関連記事】遺産分割協議書を自分で作成するための完全ガイド!基本のステップと注意点
2.3. 投資信託の評価方法
投資信託は、相続税の計算において「貸付信託受益証券」と「証券投資信託受益証券」とに分けられます。
貸付信託受益証券とは、信託財産を運用して得られた利益を受け取る権利が記載された有価証券のことをいいます。
遺産に含まれる投資信託が貸付信託受益証券の場合、信託銀行が定めた買取金額を基に、「元本の額+既経過収益額※ー源泉所得税相当額ー買取割引料」にて算出されます。
※既経過収益額とは、課税時期の属する収益計算期間の開始日からその前日までの期間に得た収益を指します。
いっぽう、証券投資信託受益証券とは、投資信託会社が集めた資金を株式会社等に投資し、その運用利益を受け取る権利が記載された証券をいいます。
遺産に含まれる投資信託が証券投資信託受益証券の場合、解約請求や買い取り請求を行った場合に証券会社等から受け取れる金額を基に、以下のように算出されます。
①中期国債ファンドやMMFなどの日々決算型証券投資信託
1口当たりの基準価格×口数×未収分配金ー源泉徴収される所得税相当額ー信託財産留保額および解約手数料
②その他の証券投資信託受益証券
課税時期の1口あたりの基準価格×口数+解約請求時に源泉徴収されるべき所得税相当額ー信託財産留保額および解約手数料
上場されている証券投資信託受益証券の場合、解約請求に基づく評価方法ではなく、上場株式の評価方法に準じて評価することになります。
【関連記事】相続時に知っておくべき株式の評価方法と手続きのポイント
【出典】No.4644 貸付信託・証券投資信託の評価(国税庁)
3.調停・審判をする場合
遺産分割協議で合意に至らなかった場合、遺産分割調停を申立てることができます。
遺産分割調停とは、相続人の一人もしくは数人から他の相続人全員を相手方とし、調停委員会を介し、話し合いで解決を目指す方法です。ここで相続人全員の合意が得られると遺産分割調停は成立し、終了となります。
いっぽう、遺産分割調停で合意に至らなかった場合には、審判手続きに移行します。この場合、裁判官が一切の事情を考慮し、審判を下すこととなります。
投資信託の相続手続きの流れと必要書類
遺産に投資信託を含む場合の相続手続きについて、以下の流れで進めましょう。
1. 金融機関に故人の死亡を伝える
投資信託の口座を管理する証券会社や信託銀行を特定し、故人の死亡を連絡します。
手元に運用報告書や取引残高証明書がある場合、これらに記載された内容を基に手続きを行うことになりますが、そうでない場合には、残高の有無を確認する手続きから始める必要があります。
この際、専用デスクから必要書類等を伝えられますので、これに従って手続きを進めることになります。
2. 金融機関に必要書類を提出する
遺産分割協議が調ったら、金融機関に必要書類を提出しましょう。
①遺言書がある場合
故人が遺言書を作成している場合、以下の書類が必要です。
- 遺言書
- 検認調書(自宅で自筆証書遺言書を発見した場合)
- 故人の死亡が確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本※
- 相続人全員分の戸籍謄本※
- 投資信託を相続する人の印鑑登録証明書
- 遺言執行者の印鑑登録証明書(選任されている場合)
- 金融機関が指定する書類
※の書類については、「法定相続情報一覧図の写し」で代用できる場合がほとんどです。
【関連記事】法定相続情報証明制度の利用手続、メリットと注意点を解説
②遺産分割協議を行った場合
遺言書がない場合や、遺産分割協議を行った場合、以下の書類が必要です。
- 遺産分割協議書
- 故人の出生から死亡までの連続する戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 金融機関が指定する書類
3. 相続人の口座開設、移管手続きを行う
必要書類を提出したら、故人の口座から相続人の証券口座への移管手続きを行います。
この場合、故人と同じ証券会社に相続人が口座を持っていない場合には、解説手続きから始めることとなります。
代償分割の場合の注意点
投資信託について、代償分割を選択した場合、原則、代償金として支払う金額に贈与税は課税されません。しかし、遺産分割協議書に「代償分割による支払いである細マーカー」旨を記載しておかなければ、贈与税がかかる可能性があります。
また、取得した相続財産より代償金が多い場合にも贈与税がかかる可能性があります。
たとえば、お父様の相続について、子である兄と弟、妹の3人が相続人だった場合。3000万円相当の投資信託について兄が受け取り、代償金として弟、妹に対し、2,000万円ずつ支払うケースでは、本来、受け取るべき金額を1,000万円超えています(3,000万円÷3人=1,000万円/人<2000万円/人)。
兄としては厚意で支払ったつもりであっても、受け取る側としては有難迷惑ということになりかねませんので、注意しましょう。
換価分割の場合は?
遺産に含まれる投資信託について、換価分割を選択した場合、原則、非課税です。ただし、遺産分割協議書にきちんと記載がなければ贈与税がかかる可能性が高いため、きちんと分割方法を明記しましょう。
おわりに
投資信託を相続する際の手続きは、しっかりとした準備と正確な書類の提出が求められます。遺言書の内容に従って進める場合や、遺産分割協議を行う場合、さらに調停や審判を経る場合、それぞれの状況に応じた手続きを適切に進めることが大切です。相続税や贈与税の負担についても十分に理解し、必要な書類や評価方法を確認することで、後々のトラブルを避けることができます。
もし不明点がある場合は、弁護士や税理士、行政書士に相談することで、円滑に相続手続きを進めましょう。