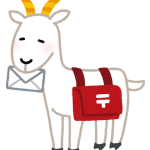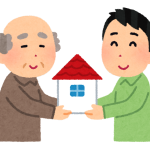当サイトの一部に広告を含みます。
Contents
関連投稿
個人事業主が従業員を雇用する際の手続
個人事業主が従業員を雇用するには、以下の手続きが必要です。
- 労働条件を通知する
- 社会保険、労働保険への加入手続き
- 税務署への届出
- 給与明細、源泉徴収等の準備
1.労働条件を通知する
従業員を雇用する場合、労働条件を通知する必要があります。これに伴い、労働条件通知書を作成し、当該従業員に共有します。
①労働条件通知書の記載内容
労働条件通知書には、以下の内容を記載します。
- 契約期間
- 契約更新の基準
- 就業場所と仕事の内容
- 始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日、休暇、シフトに関する事項
- 賃金の決定、計算と支払方法、締め日と支払時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項
※解雇事由を含みます - 退職手当の対象、退職手当の決定、計算と支払方法、退職手当の支払時期に関する事項
- 臨時に支払われる賃金※、賞与とこれらに準ずる賃金と最低賃金に関する事項
- 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
- 安全と衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償と業務外の疾病扶助に関する事項
- 表彰と制裁に関する事項
- 休職に関する事項
労働通知書に決まった様式はなく、どこかに提出する必要もありませんが、厚生労働省が公表する以下のテンプレートを使用することで漏れがなく、安心して交付することができます。
【関連リンク】令和6年4月から労働条件明治のルールが変わりますー滋賀労働局(厚生労働省)
2.社会保険、労働保険への加入手続き
①社会保険の手続き
個人事業主であっても、一定の業種で常時5人以上を雇用する事業所では、農林漁業、サービス業等の場合を除き、社会保険が強制的に適用されます。社会保険とは、健康保険や厚生年金保険、介護保険の総称です。
仮にパートやアルバイトの場合でも、1日、または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上の場合には加入が義務付けられます。保険料については、労使折半で負担し、日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)に届出書を提出する必要があります。
一定の業種には、製造業や建設業(土木建築業)、鉱業、電気ガス事業、運送業、貨物積み下ろし業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告工業、教育研究調査業、医療保険業、通信報道業、社会福祉業、弁護士業等が含まれます。
②労働保険の手続き
従業員を1人でも雇用する場合、業種や規模を問わず、事業主は労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を負担する必要があります。労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
具体的に加入の対象となるのは、いかに該当する場合です。
- 引き続き31日以上の雇用見込みがある場合
- 1週間の所定労働日数が20時間以上の場合
3.税務署への届出
従業員を雇用し、給与を支払う場合には、給与からあらかじめ所得税を引き、源泉徴収を行う必要があります。そのため、従業員を初めて雇用した日した日から1か月以内に、税務署に対し「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出しましょう。
【関連リンク】A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出(国税庁)
4.給与明細、源泉徴収等の準備
従業員を雇用した場合、労働者名簿と賃金台帳を作成する必要があります。
①労働者名簿
労働者名簿とは、従業員の氏名や住所、雇用年月日等の情報を記載した書類をいいます。この名簿は、従業員が1人でもいれば作成が義務付けられ、違反した場合には、30万円以下の罰金が科されます。
労働者名簿と従業員名簿に違いはないものの、労働基準法には「労働者名簿」と規定されていることから、迷った場合にはこれに合わせると安心です。
労働者名簿には、以下を記載する必要があります。
- 氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 雇入れの年月日
- 退職の年月日およびその事由
- 死亡の年月日およびその原因
【参考】様式第十九号(第五十三条関係)労働者名簿(厚生労働省)
②賃金台帳
賃金台帳とは、従業員の氏名や性別、労働日数、賃金の計算期間、給与の支払状況等を記載した書類を指し、支払の都度、遅滞なく記入しなければなりません。記載すべき内容は、以下の通りです。
- 氏名
- 性別
- 賃金の計算期間
- 労働日数と時間数
- 時間外労働や休日労働、深夜労働の労働時間数
- 基本給や手当等の種類と金額
- 控除の項目と金額
賃金台帳は、最後に記入した日から5年間保存する義務がありますので、記入の都度、当時の年月日がわかるようにしておくと管理しやすいかと思います。この点、Excelや専用ソフト等の電子データで管理するのがオススメですが、労働基準監督署の臨検時には、すぐに担当者に提示できる状態にしておかなければならない点には注意が必要です。
③給与明細書
給与明細とは、従業員の勤怠情報や給与の支給額、控除額等を記載する書類です。給与明細について、所得税法により個人事業主から従業員に対し、提示が義務づけられていますが、賃金台帳のように保存義務はありません。
給与明細書の記載内容は、以下の通りです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 勤怠項目 | ・就業日数や出勤日数、労働時間数 ・欠勤日数や休日出勤の日数 ・有休取得状況と有給の残日数 ・普通残業時間や深夜残業時間、休日労働時間、遅刻または早退の有無と時間 |
| 支給項目 | ・基本給 ・各種手当(役職手当、資格手当、住宅手当、家族手当、通勤手当、残業手当、深夜勤務手当、休日出勤手当など) ・欠勤控除、遅刻 ・早退控除 ・総支給額 |
| 控除項目 | ・社会保険料(健康保険料、雇用保険料、厚生年金保険料、介護保険料) ・税金(所得税、住民税) ・その他 |
④源泉徴収の準備
源泉徴収額は、国税庁が公表する「給与所得の源泉徴収税額表」を基に算出します。
【関連リンク】給与所得の源泉徴収税額表(令和7年度)
源泉所得税の納付期限は、原則、徴収した日の翌月10日ですが、給与を支払う従業員が10人未満の場合、毎年7月10日と翌年1月20日の2回納付が認められる場合があります。
【出典】A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請(国税庁)
建設業の個人事業主が従業員を使う場合の注意点
建設業を営む個人事業主様が従業員等を使う場合、以下に注意しましょう。
1.契約形態
建設業の個人事業主様が従業員を使う場合、「雇用契約」または「業務委託契約」を選択することになります。
①雇用契約
雇用契約とは、事業主から支持を受け時間単位で働く契約をいいます。社会保険への加入が求められ、給与支給時に源泉所得税を控除し、給与明細を発行する必要があります。
②業務委託契約
業務委託契約とは、特定の成果を提供する契約をいい、外注費として処理することになりますので、源泉所得税の控除は扶養です。
2.契約を明確にする
契約内容が不明確ですと、支払が「外注費」「賃金給料」のいずれに該当するのかがわからず、税務処理にて混乱を招くおそれがあります。確定申告時にも対応が異なりますので、契約内容は明確化し、それに伴った手続を適切に行う必要があります。
3.説明義務
個人事業主が従業員を雇用する場合や、業務委託契約を締結する場合、相手方に対し、その契約内容を適切に説明しなければなりません。これを怠った場合、税務申告時に問題が生じる可能性があるだけでなく、当事者間におけるトラブル発生リスクも負うことになります。
Q.建設業の個人事業主同士において、互いを従業員にすれば個人事業主の弱点を補えると思うのですが…
A. 一見、名案に見えますが、以下のリスクに注意してください。
①社会保険への加入要件
社会保険の加入対象は、労働契約に基づく従業員であり、一定時間・日数を超える就業実態がなければなりません。ですので、互いに相手の従業員として他方の業務に従事し続けられるかどうかを検討する必要があります。
②不正行為に該当する可能性
仮に労働契約を結ばず、付随する必要な手続等を怠った状態で従業員として扱った場合、不正行為に該当する可能性が高いです。社会保険制度は、事実関係に基づき設計されていることから、一部でも架空の関係が存在すれば法令違反として罰則対象となります。
③税務署や社会保険事務所の監査
税務署や社会保険事務所からの監査により、不正を指摘される場合があります。その場合、社会保険料や税金の未納分、さらに追徴課税が課されることもあります。また、不正加入と見なされた場合には、労働基準法等に基づくキツい罰則が適用されるかもしれません。
以上を踏まえ、以下に代替案を挙げます。
①業務委託契約を活用する
既に活用されているかと思いますが、お互いに個人事業主様でしたら業務委託契約が望ましいです。業務委託契約の場合、雇用契約とは異なり、従業員としての福利厚生は適用対象外となりますが、国民健康保険や国民年金保険のほか、小規模企業共済、iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入が可能です。
これらの保険料や事業経費として計上することはできませんが、個人の所得税における「社会保険料控除」の適用が受けられます。
また、生命保険に加入している場合の支払保険料や、個人年金保険料を支払っている場合には、その一部について「生命保険料控除」の対象です。この場合、最大12万円まで当て起用を受けられます。
②合同会社(LLC)または株式会社を設立する
個人事業主同士で合同会社(LLC)や株式会社を設立する方法もあります。法人化することにより社会保険に加入できるだけでなく、事業主自身も法人役員として社会保険に加入できる場合があります。
ただし、個人事業に比べると法人の運営には会計・税務の処理コストが発生します。これらの点を十分検討しましょう。
おわりに
個人事業主が従業員を雇用するには、さまざまな手続きと責任が伴います。労働条件通知書の作成や社会保険、労働保険への加入手続き、税務署への届出などを適切に行うほか、契約形態や契約内容を明確にし、従業員や業務委託先に対する説明義務を果たすことにより、後々のトラブルを避けることができるかと思います。
ご不明な点や不安なことがございましたら、お近くの官公署、または社労士までご相談ください。