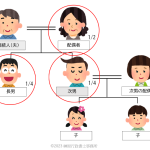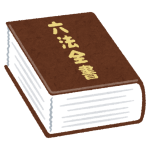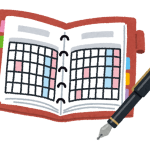当サイトの一部にアフィリエイト広告を含みます。
介護保険制度は、高齢者が自立した生活を維持できるよう支援する重要な制度です。特に要介護認定は、どれくらいの介護が必要かを判定し、適切なサービスを受けるためには必須です。
本記事では、要介護認定の手続きの流れや、介護予防サービスの内容について詳しく説明します。これらの情報を理解することで、必要なサービスをスムーズに利用し、生活の質を向上させることができます。
要介護認定とは
要介護認定とは、介護が必要な状態かどうかを判断し、その程度を示す制度をいいます。要介護認定を受けるには、以下の手続きが必要です。
要介護認定手続きの流れ
要介護認定の流れは、以下の通りです。
- 要介護認定を申請する
- 申請書の提出
- 訪問調査
- 一次判定
- 二次判定
- 要介護認定の通知
- ケアプラン作成
- サービスの利用開始
1.要介護認定を申請する
①申請先
要介護認定の申請先は、お住いの市区町村です。
要介護認定の申請は、日常生活に助けが必要であったり、入院中の方が退院後の暮らしに不安を抱いたときに検討するケースがほとんどですが、申請時期は個人で決めることができます。
②申請できる人
申請できる人は、以下の通りです。
- ご本人
- ご家族
- 成年後見人
- 地域高齢者支援センター
- 指定居宅介護支援事業者
- 入居している介護保険施設等の職員
- 入居している有料老人ホーム等の職員
要介護認定を受けられる人
要介護認定を受けられる人は、年齢により下表のように分けられます。
| 65歳以上の人 (第1号被保険者) | 原因を問わず、介護や支援が必要となった人 |
| 40歳から64歳までの人 (第2号被保険者) | 特定疾病※が原因で介護や支援が必要になった人で、医療保険に加入している人 👉交通事故やけがなど、特定疾病以外の原因による場合は介護保険の対象外です |
※特定疾病とは
特定疾病とは、加齢と関係がある以下の16種類の疾病を指します。
- がん
- 脊柱管狭窄症
- 関節リウマチ
- 早老症
- 筋萎縮性側索硬化症
- 多系統萎縮症
- 後縦靭帯骨化症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 脳血管疾患
- 初老期における認知症
- 閉塞性動脈硬化症
- 進行性格上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 慢性閉塞性肺疾患
- 脊椎小脳変性症
- 両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性膝関節症
2.申請書の提出
申請時に必要な書類は、以下の通りです。
| ☐ | 要介護認定申請書 | |
| ☐ | 介護保険被保険者証 (65歳以上の人) | 原本 |
| ☐ | マイナ保険証 (64歳以下の人) | マイナ保険証がない場合は、医療保険者が発行する「資格確認書」 |
| ☐ | 身分証明書 | 申請者、または申請代行者の写真付きの身分証明書 |
| ☐ | 主治医の情報が確認できるもの | 主治医の氏名、医療機関名、診療科目、所在地、電話番号がわかるもの |
3.訪問調査
申請後、自治体から委託を受けた調査員が、自宅、入居施設、入院先の医療機関などを訪問し、心身の状況などの基本調査を行います。加えて、家族状況や住宅環境、既往歴等の概況調査、基本調査項目だけではわからない特記事項について、本人や家族から聞き取り調査を行うことになります。
| 主な調査項目 | ||
|---|---|---|
| ・麻痺の有無 ・拘縮の有無 ・寝返り ・起き上がり ・座位保持 ・両足での立位保持 ・歩行 ・移乗 ・移動 ・立ち上がり | ・片足での立位 ・洗身 ・嚥下 ・食事摂取 ・排尿 ・排便 ・清潔 ・衣服着脱 ・薬の内服 ・金銭の管理 | ・日常の意思決定 ・視力 ・聴力 ・意思の伝達 ・記憶、理解 ・物忘れ ・大声を出す ・過去14日間に受けた医療 ・日常生活自立度 ・外出頻度 など |
①主治医に意見書の作成を依頼
自治体から主治医に対し、心身の状況についての意見書作成を依頼します。主治医とは、介護が必要となった直接の原因である疾病を治療する医師や、かかりつけの医師など、本人の心身の状況をよく理解している医師をいいます。
主治医の意見書には病名や症状のほか、身体の細かい状態まで記入してもらうことになりますので、早めにかかりつけ医を見つけておきましょう。
4.一次判定
認定調査票と主治医からの意見書が揃った時点でコンピュータ処理が行われ、要介護状態区分が自動的に判定されます。ここでの結果は通知されません。
5.二次判定
二次判定では、一次判定の結果を基に、自治体が任命する「医療」「保険」「福祉」の専門家で構成する介護認定審査会において、要介護状態区分と有効期間を決定します。
介護認定審査会では、一次判定の結果に加え、認定調査票の特記事項や主治医の意見書に記載された内容を基にコンピュータでは半的出来ない個々の介護の必要性について話し合われます。
要介護状態区分は、介護にかかる手間により異なるため、病気の重症度と必ずしも一致するものではない点に注意しましょう。
①二次判定でのチェック項目
- 調査票の特記事項
- 主治医意見書
👉診察の状況
👉特別な医療
👉心身状態に関する意見
👉介護に関する意見
6.要介護認定の通知
介護認定審査会の判定結果に基づき、下表の区分に認定されます。結果が記載された認定結果通知書と要介護状態区分が記載された新しい介護保険被保険者ほうが郵送されますので、すぐに確認しましょう。
| 要介護状態区分 | 状態の目安 | 利用できるサービス・事業 |
|---|---|---|
| 要支援1 | ほぼ自立した生活ができるが、介護予防のための支援や改善が必要 | ・介護予防サービス ・介護予防・日常生活支援総合事業 |
| 要支援2 | 日常生活に支援は必要だが、それにより介護予防できる可能性が高い | |
| 要介護1 | 歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要 | 介護サービス |
| 要介護2 | 歩行などが不安定で、排泄や入浴などの一部または全部に介護が必要 | |
| 要介護3 | 歩行や排泄、入浴、衣服の着脱などにほぼ全面的な介護が必要 | |
| 要介護4 | 日所生活全般に動作能力が低下しており、介護なしでの生活は困難 | |
| 要介護5 | 生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能 | |
| 非該当 | 要支援や要介護にあてはまらない | ー |
①認定結果に不服があるとき
要介護認定の結果に疑問や納得できない部分がある場合、自治体までご相談ください。それでも納得いかない場合、県に設置される「介護保険審査会」に対し、審査請求することができます。申立期限は、結果通知を受け取った日から3か月以内です。
7.ケアプラン作成
①要支援1・2の場合
要支援1、または2の認定となった場合、介護サービスの利用には、以下の手続きが必要です。
- 担当地区の地域高齢者支援センターに連絡
- 「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書」を提出
- ケアマネジャーとケアプランの作成
- サービス事業者と契約
- 介護予防サービスの利用へ
②要介護1~5の場合
要介護1~5認定の場合、サービスの利用には以下の手続きが必要です。
- 希望する施設の種類を決める
- 直接、希望する施設に「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書」を提出
- ケアマネジャーとケアプランを作成
- サービス事業者と契約
- 介護サービスの利用へ
8.サービスの利用開始
ケアマネジャーと作成したケアプランに基づき、介護保険サービスの利用が始まります。ケアプランに記載のないサービスは利用できないため、新たに利用したいサービスが生じた場合は、担当のケアマネジャーに相談する必要があります。
要介護認定の有効期間
要介護認定の結果について、新規の場合は6か月、更新の場合は12か月の有効期間があります。
| 対象 | 有効期間 |
|---|---|
| 新規 | 6か月~12か月 |
| 要介護認定の更新 | 12か月=36か月 |
要介護認定に自動更新はありませんので、継続的に利用したい場合には、更新手続きが必要です。
認定の効力発生日は認定申請日ですが、更新認定の場合、前回認定の有効期間満了日の翌日です。
要介護認定の更新申請
要介護認定の更新手続きは、有効期間満了日の60日前から行うことができます。
①要介護認定の更新申請について
要介護認定の更新申請は、住所地の市区町村役所、または地域包括支援センターにて行うことができます。
申請後は、認定審査員が訪問調査を行い、認定調査票を作成します。同時に、主治医意見書の作成を本人のかかりつけ医に依頼します。これらが揃った時点で介護認定審査会における審査が行われ、要介護区分と有効期間が決定されることになります。
②区分変更申請について
認定の有効期間内において、心身の状態に大きな変化があった場合には、いつでも区分変更申請をすることができます。申請から認定までの流れは、新規申請の場合と同じです。
新規申請、更新申請、区分変更申請、いずれの場合でも、古い被保険者証がある場合には市区町村役所まで返還しましょう。
要支援1・2の場合に受けられるサービス
要介護状態区分に非該当だった場合でも、一定要件を満たすと「介護予防・日常生活支援総合事業」を受けられるケースがあります。
介護予防とは
介護予防とは、できる限り要介護状態にならないようにすることに加え、介護が必要な状態であっても悪化の防止を図り、軽減を目指すことをいいます。
介護予防のための生活機能チェックリスト
非該当の人が介護予防サービス等を受けられるのは、下表のチェックリストで生活機能の低下がみられる場合です。
| No | 質問項目 | いずれかに○ | |
|---|---|---|---|
| 1 | バスや電車で1人で外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 2 | 日用品の買い物をしていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 3 | 預貯金の出し入れをしていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 4 | 友人の家を訪ねていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 5 | 家族や友人の相談にのっていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 6 | 階段や手すりや壁をつたわずに昇っていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずにたちあがっていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 8 | 15分くらい続けて歩いていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 9 | この1年間に転んだことがありますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 10 | 転倒に対する不安は大きい手ですか | 1.はい | 0.いいえ |
| 11 | 6か月間で2~3㎏以上の体重減少がありましたか | 1.はい | 0.いいえ |
| 12 | 身長 ㎝ 体重 ㎏(BMI= )※ | ||
| 13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | 1.はい | 0.いいえ |
| 14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 15 | 口の渇きが気になりますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 16 | 週に1回は外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 17 | 去年と比べて外出の回数が減っていますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 18 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあるといわれますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | 1.はい | 0.いいえ |
| 22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | 1.はい | 0.いいえ |
| 23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | 1.はい | 0.いいえ |
| 24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | 1.はい | 0.いいえ |
| 25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | 1.はい | 0.いいえ |
※BMI(=体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m)が18.5未満の場合に該当とする。
介護予防サービスとは
介護予防サービスとは、生活機能の維持改善、QOLの向上などを目指し、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう支援するサービスをいいます。
介護予防サービスの対象者
介護予防サービスの対象者は、以下に該当する人です。
- 「要支援1」または「要支援2」の認定を受けた人
- 総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の対象となる人
介護予防の取り組み
介護予防サービスの具体的な内容について、以下に紹介します。
①運動機能の向上
運動器の機能向上を通じ、生活機能の改善を図る支援です。理学療法士等を中心に看護職員や介護職員等が協働し、有酸素運動、ストレッチ、簡単な器具を使った運動などを行います。
②栄養状態の改善
食事の内容などを見直し、低栄養を予防・改善する支援です。管理栄養士が看護職員や介護職員等と連携し、栄養状態を改善するためのサービス計画を個別に作成し、栄養相談や集団的な栄養教育などを行います。
③口腔機能の向上
口腔内の機能を向上することにより、美味しく、楽しく、安全な食生活を送れるよう支援するものです。歯科衛生士等が看護職員や介護職員と協働し、食べる、飲み込む機能訓練や、口腔清掃の自立支援を行います。
④閉じこもり予防
閉じこもりを防ぎ、より活動的な生活を送れるよう支援します。
⑤認知症の予防
認知機能の低下を予防するため、運動や知的活動を取り入れた生活を継続できるよう支援します。
⑥うつの予防
高齢者のうつ予防、早期発見・早期治療、地域の環境づくりなどにより心の健康向上を図ります。
介護予防サービスを利用するまでの流れ
介護予防サービスを利用するには、以下の手続きが必要です。
- お住いの市区町村役所へ要介護(要支援)認定の申請を行う
- 要介護認定
- 介護予防ケアプランの作成
介護予防サービスの種類
介護予防サービスには、以下のようなものがあります。
| 居宅で受けられるサービス | 訪問型サービス(ホームヘルプ) |
| 介護予防訪問入浴介護 | |
| 介護予防訪問看護 | |
| 介護予防訪問リハビリテーション | |
| 介護予防居宅療養管理指導 | |
| 施設等で受けられるサービス | 通所型サービス(デイサービス) |
| 介護予防通所リハビリテーション(デイケア) | |
| 介護予防短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ) | |
| 介護予防短期入所療養介護(医療施設のショートステイ) | |
| 介護予防特定施設入所者生活介護 | |
| 地域密着型のサービス | 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 ※要支援2のみ | |
| その他 | 介護予防福祉用具貸与 |
| 特定介護予防福祉用具販売 | |
| 介護予防住宅改修費の支給 |
居宅で受けられる介護予防サービス
訪問型サービス(ホームヘルプ)
訪問型サービスとは、ホームヘルパーやボランティア、保険、医療の専門職などが利用者の自宅を訪問し、生活支援や相談、指導、移動支援などを行うものです。
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護とは、看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、入浴の介護を行うものです。ただし、要支援者ならどなたでも利用できるものではなく、自宅に浴室がない場合や、病気やケガ等により入浴ができない場合に限ります。
介護予防訪問看護
介護予防訪問看護とは、医師の指示に基づき看護師等が利用者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や、診察の保護を行います。
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーションとは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持・回復や、日常生活の自立を目指し、リハビリテーションを行うものです。
介護予防居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導とは、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が利用者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導、助言等を行うものです。
施設等で受けられる介護予防サービス
通所型サービス(デイサービス)
通所型サービス(デイサービス)とは、デイサービスセンター等に日帰りで通い、生活機能向上のための機能訓練やレクリエーション等に参加することができます。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)とは、介護老人保健施設や介護医療院、病院、または診療所に日帰りで通い、日常生活上の支援や生活行為の向上を目指した支援、リハビリテーションを受けるものです。加えて、本人の目標に合わせ、選択的サービスも提供されます。
介護予防短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
介護予防短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)とは、特別養護老人ホーム等の福祉施設に短期滞在し、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを受けるものです。普段、支援してくれる家族が病気やけがで動けなくなったときに限らず、旅行や休息のために利用されるケースもあります。
介護予防短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
介護予防短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)とは、介護老人保健施設等の医療施設に短期滞在し、介護予防を目的とした医療的ケア、日常生活上の支援や機能訓練を受けらるものです。本人のQOL向上だけでなく、ご家族の身体的・精神的な負担軽減を目的としています。
介護予防特定施設入所者生活介護
介護予防特定施設入所者生活介護とは、介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入居している人に対し、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練を提供するものです。
地域密着型の介護予防サービス
地域密着型の介護予防サービスは、自治体によりサービスの種類や内容が異なりますが、以下に一般的な例を挙げます。
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護とは、本人の要望に応じ、施設への通所、自宅への訪問、短期間の宿泊(滞在)を組み合わせるものです。
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護とは、老人デイサービスセンター等の施設において、認知症の人を対象とした専門的なケアを受けられるものです。
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護とは、介護スタッフのサポートを受けながら、共同生活を送る認知症の人を支援するものです。
その他
介護予防福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与とは、福祉用具の貸与により、本人の日常生活における自立支援や、介護をする人の身体的な負担を軽減するものです。福祉用具のうち介護予防に有効なものが貸与の対象となります。以下に、例を挙げます。
- 手すりやスロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器、歩行補助杖
- 入浴補助用具
- 食事補助用具 など
特定介護予防福祉用具販売
特定介護予防福祉用具販売とは、自治体より指定を受けた事業者が販売する福祉用具を購入した場合、一定額を上限に給付金がもらえるものです。対象となるのは「貸与になじまない福祉用具」で、上限額を超える部分は自己負担になる点に注意しましょう。
- 歩行補助具
- 座位保持や体位保持用具
- 入浴補助用具
- 食事補助具
- トイレ補助具 など
介護予防住宅改修費の支給
介護予防住宅改修費の支給とは、本人が住み慣れた自宅で暮らし続ける目的で住宅の改修を行った場合、原則20万円まで支給されるものです。支給を受けるには、改修工事の前に自治体に申請し、必要と認められる部分についてのみ対象となる点に注意しましょう。以下は、一例です。
- 手すりの取り付け
👉老化や階段、トイレ、浴室など - 段差の解消
👉スロープ設置や床の変更など - 床材
👉滑りにくい床材への変更 - 扉
👉開き戸から引き戸への変更など - トイレ
👉便座の高さ調整や手すりの設置、広さ確保など - 浴室
👉浴槽のまたぎ高さの低減、滑りにくい床材への変更など - キッチン、洗面所
👉作業導線の改善、使いやすい設備への変更など
一般介護予防事業(総合事業)
要介護認定で「非該当」になった人のうち、65歳以上のすべての人と、その支援を行う人が利用できるのが「一般介護予防事業」です。一般介護予防事業は、以下に分類されます。
- 介護予防把握事業
- 介護予防普及啓発事業
- 地域介護予防活動支援事業
- 一般介護予防事業評価事業
- 地域リハビリテーション活動支援事業
自治体により提供するサービス内容が異なるため、お住いの市区町村までご確認ください。
おわりに
要介護認定や介護予防サービスの利用は、生活の質を保つために重要なステップです。自分や家族がどのようなサポートを必要としているのかを理解し、適切な手続きを行うことが、健康で安心した生活を支える基盤となります。介護保険に関する疑問や不安がある場合は、地域の介護保険担当窓口に相談し、必要なサポートをしっかりと受けましょう。