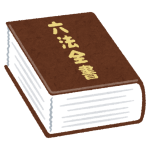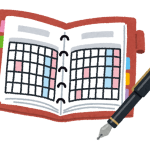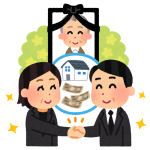当サイトの一部にアフィリエイト広告を含みます。
Contents
「認知症の家族が相続人だったら、どうなるの?」
相続手続きを進めようとしたとき、相続人の中に認知症の方がいると、手続きがスムーズにいかないことがあります。相続では、すべての相続人の合意が必要な場も多く、判断能力が低下している方がいると成立しない可能性もあります。
この記事では、認知症の相続人がいる場合の注意点から、成年後見制度の仕組み、手続きの流れ、さらには事前にできる対策までをわかりやすく解説します。ご家族にとって、将来の安心につながるヒントになれば幸いです。
【関連記事】相続の基本ステップ:遺産調査から承継手続きまでの流れ
認知症の相続人がいる場合
故人の相続手続きにおいて、相続人の中に認知症の親族が含まれる場合、遺産分割協議ができない可能性があります。
遺産分割協議とは、遺産について、誰が、何を、どのように承継するかを話し合うもので、すべての相続人が参加し、合意に至らなければ無効となります。そのため、認知症だからといって参加させなければ、その話し合い自体が無効となるおそれがあるのです。
【関連記事】遺産分割協議の進め方、期限、注意点を解説
法定相続分による分割
法定相続分とは、民法に定められる相続方法をいいます。この方法で遺産を分割する場合、遺産分割協議は不要なため、認知症の相続人の参加が問われることはありません。
しかし、法定相続分で分割する場合であっても、相続手続きの中で、すべての相続人の押印と印鑑登録証明書を求められる場面も多く、認知症の相続人抜きでの相続手続きは、事実上困難だと言わざるを得ません。
遺産分割協議が必要な場合
故人が遺言書を作成していない場合や、遺言書の内容と異なる分割方法を希望する場合、遺産分割協議により遺産を分割することになります。遺産分割協議にはすべての相続人が参加しなければならないため、認知症の相続人には代理人が必要です。
認知症の相続人の代理人とは
認知症の相続人の代理人として、成年後見人が考えられます。成年後見人とは、認知症等で判断能力が著しく低下した人を支援する人をいい、家庭裁判所により専任されます。
成年後見人は、本人の財産管理のほか、契約などの法律行為を行う権限をもちます。相続手続きにおいては、遺産分割協議や相続放棄、名義変更手続きなどを行うことができます。
成年後見人の選任手続き
認知症の相続人を代理する目的で成年後見人を選任するには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
①申立先
成年後見人の選任は、認知症の方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
②申立てができる人
申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長、検察官です。具体的には、以下の通りです。
- 本人
- 配偶者
- 4親等内の親族
(親、祖父母、曾祖父母、子、孫、ひ孫)
(兄弟姉妹、おじ、おば、甥姪、いとこ)
(配偶者の親、祖父母、曾祖父母、子、孫、ひ孫)
(配偶者の兄弟姉妹、おじ、おば、甥姪 など) - 成年後見人・保佐人・補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
- 成年後見監督人等
- 市区町村長
- 検察官
③申立てに必要な書類
申立てに必要な書類は、以下の通りです。
| 必要書類等 | 取得先等 | |
|---|---|---|
| 1 | 後見・保佐・補助開始申立書 | |
| 申立事情説明書 | ||
| 親族関係図 | ||
| 本人の財産目録及びその資料 | ||
| 相続財産目録およびその資料 ・預貯金通帳のコピー ・保険証券のコピー ・株式・投資信託等の資料のコピー ・不動産の全部事項証明書 ・債権・負債等の資料のコピー | ・保険証券が手元にない場合、保険契約が記載された通知書等のコピー ・不動産の全部事項証明書は、おみょりの法務局で入手することができます | |
| 本人の収支予定表およびその資料 ・収入に関する資料のコピー ・支出に関する資料のコピー | 毎月発生する収入・支出関係については、直近のものを提出します | |
| 親族の意見書 | ||
| 後見人等候補者事情説明書 ・後見人等と本人との間で、金銭の貸借、担保提供、保証、立替えがある場合にはその関係資料のコピー | ||
| 2 | 診断書(成年後見制度用) | |
| 診断書付票 | ||
| 本人情報シート(コピー) | ||
| 3 | 本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 各自治体の担当窓口 |
| 4 | 本人の住民票または戸籍の附票 | |
| 後見人等候補者の住民票または戸籍の附票 | ||
| 5 | 本人が登記されていないことの証明書 |
④かかる費用
成年後見人の申立てには、以下の費用がかかります。
| 必要書類等 | 取得先 | |
|---|---|---|
| 1 | 収入印紙 ①申立手数料 800円分 ②登記手数料 2,600円分 | 郵便局など |
| 2 | 郵便切手(送達・送付費用) | |
| 3 | 鑑定費用 |
郵便切手は、申立先となる家庭裁判所により必要な金額と組み合わせが異なりますので、事前にご確認ください。
成年後見人申立てから終了までの流れ
成年後見人の選任申立てについて、以下の流れで進むことになります。
- 申立準備
- 面接予約
- 申立て
- 審理
・書類審査
・面接
・親族への意向照会
・鑑定
・本人、候補者調査 - 審判、確定、登記
- 職務説明
- 初回報告
- 定期報告
- 後見等の終了
1.申立準備
申立先となる家庭裁判所と申立てができる人を確認し、申立ての準備を行います。
2.面接予約
家庭裁判所により、申立ての前に面接が実施されます。申立先である家庭裁判所に確認しましょう。
申立先により異なりますが、申立人と認知症の相続人から、申立てに至る事情を聞かれるケースが多いです。面接時に必要書類の確認も行われることから、できるだけ不備がないように揃えましょう。
3.申立て
面接が終了し、必要書類が揃ったら申立手数料等を支払い、申立てとなります。
4.審理
①書類審査
家庭裁判所は、必要書類の過不足や、記入内容について審査を行います。
②面接
あらかじめ予約した日時に、家庭裁判所で面接が行われます。この際、申立書に使用した印鑑、申立書類の控え等が必要です。そのほか、担当者から事前に連絡があった場合には、指示に従いましょう。
面接の所要時間は、概ね1~2時間程度です。
③親族への意向照会
家庭裁判所から、審理の参考として本人の親族に対し、申立ての概要および成年後見人等候補者の氏名を開示され、これらに関する意向を確認されるケースがあります。
④鑑定
鑑定とは、本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するための手続きです。申立の際に医師の診断書を添付しますが、これとは別に、家庭裁判所から依頼された医師により鑑定が行われます。
鑑定費用について、鑑定人の意向や鑑定のために要する労力等を踏まえ、一般的に10万~20万円程度の費用がかかります。この費用は、鑑定が必要な場合に家庭裁判所から連絡がありますので、その期間内に収めることとなります。
⑤本人、候補者調査
成年後見制度では、本人の意思を尊重するため、申立ての内容などについて本人から直接意見を聴く「本人調査」を行われることがあります。基本的には、本人が家庭裁判所に足を運ばなければなりませんが、入院や体調などにより難しい場合、家庭裁判所の担当者が入院先等に来てくれることもあります。
成年後見人には、家庭裁判所が最も適任だと考える人を選任するため、申立書に記載した候補者が必ず選任されるとは限りません。また、家庭裁判所の判断に対し、不服申立てをすることはできない点に注意しましょう。
※候補者になれない人
以下に該当する場合、成年後見人になることはできません。
- 未成年者
- 家庭裁判所から成年後見人、保佐人、補助人等を解任されたことがある人
- 破産開始決定を受けたが、復権していない人
- 現在、本人との間で訴訟をしている、または過去に訴訟をした人
- 現在、本人との間で訴訟をしている、または過去に訴訟をした人の配偶者、親、または子
- 行方不明の人
また、以下に該当する場合には、候補者以外の人が選任されたり、成年後見等監督人を選任される可能性が高いです。
- 相続において、親族間に争いがあるとき
👉感情的な対立がある場合、公平な立場の専門が必要 - 財産の種類や金額が多いとき
👉管理が複雑化するため、経験豊富な人が必要 - 不動産の売却や保険金の受け取りが関わるとき
👉重要な法律手続きについて、正確な対応が求められる - 後見人になろうとしている人と本人の利益がぶつかるとき
👉たとえば、相続内容で利害関係がある場合、第三者が代理することに - お金の貸し借り、立替があるとき
👉お金のやり取りについて、中立な調査が必要 - これまで本人との接点があまりなかったとき
👉親族でも日常的なかかわりが薄いと専門家が選ばれることも - 収入や支出が不安定、または管理が難しいとき
👉家計の管理に客観的な視点が必要だと判断された場合 - 生活費のやりくりが本人と混ざっているとき
👉お金の流れを明確にするため、専門家が必要 - 申立書に不備や不明点があるとき
👉財産目録などが不十分な場合、裁判所が慎重になる - 後見人候補が不安を感じているとき
👉相談できる専門職が補助する形が望ましい - 後見人候補者が本人の財産を使う予定があるとき
👉利用目的が自分のためであれば、専門家によるチェックが必要 - 財産運用が目的の場合
👉後見はあくまで「守る」ための制度なので、投資目的だと認められづらい - 健康問題や多忙により、後見業務が難しいと判断されたとき
- 訴訟・調停・債務整理などの予定があるとき
👉法的なトラブルに対応できるよう、法律の専門家が必要 - 財産の内容がよくわからないとき
👉全体像をつかむために、調査できる人が必要
5.審判、確定、登記
鑑定や調査の終了後、家庭裁判所は後見開始の審判をし、併せて、最も適任と思われる人を成年後見人に選任します。成年後見人は複数選任されることもありますし、成年後見監督人が選任されることもあります。
審判の内容は申立人、本人、成年後見人等に書面で通知されます。この書面が届いてから2週間以内に不服申立てがなければ、後見等開始審判が確定します。
そのため、開始審判に不服がある場合、審判から2週間以内に即時抗告の手続きをとらなければなりません。ただし、成年後見人に選任された人についての不服を申し立てることはできない点に注意しましょう。
後見開始審判が確定すると、家庭裁判所は法務局に審判内容を登記するよう依頼します。
6.職務説明
成年後見人に選任された人を対象に、家庭裁判所から職務説明の案内があります。
7.初回報告
成年後見人は、はじめに本人の財産状況を調査し、財産目録および年間収支予定表を作成し、資料を添えて、家庭裁判所に提出しなければなりません。この初回報告が終わるまでの間、成年後見人として本人を代理する行為等はできません。
8.定期報告
成年後見人に選任されると、定期的かつ自主的に、本人の現状や現在の問題等についての報告書、本人の財産目録、その裏付けとなる書類等を家庭裁判所に提出する必要があります。そのため、日頃から領収書などの取引に関する書類は保管し、収支状況を把握しなければなりません。
9.後見等の終了
成年後見人の仕事が終わるのは、以下の場合です。
- 本人が死亡したとき
- 成年後見人の辞任
- 本人の能力が回復し、後見等開始の取消しの審判がなされたとき
逆に言えば、これらの事由が生じない限り、成年後見人を辞めることはできません。
【生前対策】認知症の家族がいる場合
相続開始前において、推定相続人の中に認知症の方がいる場合には、以下の対策が講じましょう。
1.遺言書を作成する
相続において、遺言書の内容は最優先事項となります。有効な遺言書を作成することで、遺産分割協議を行うことなく遺産を分割することができます。
【関連記事】遺言書の種類、メリット、注意点を解説
2.家族信託を活用する
家族信託の活用も有効です。家族信託とは、あらかじめ目的と財産を特定し、信頼できる家族に対し、財産の管理・運用を託す制度です。
特定の財産について承継先を決めておくことで、遺産分割協議で迷うこともありません。
【関連記事】家族信託の活用方法、メリット、注意点を解説
3.生前贈与を検討する
自分の財産について希望がある場合、生前贈与も選択肢の一つです。ただし、控除枠を超えると贈与税がかかる点には注意が必要です。
【関連記事】贈与と相続、どっちがベスト?終活の財産管理の選択肢を解説
【関連記事】生前贈与の非課税枠、注意点を解説
おわりに
相続は、法律だけでなくご家族の気持ちも大切にしたい手続きです。認知症の相続人がいるケースでは、専門的な対応が求められることが多くなりますが、あらかじめ制度を知っておくことで、心の準備も整います。
また、生前のうちに遺言書や家族信託などの対策を講じておくことで、将来のトラブルを未然に防ぐことも可能です。
必要に応じ、信頼できる専門家に相談することも選択肢の一つ。ご家族みんなが納得できる形で、大切な財産と想いをつなぐお手伝いになればと思います。