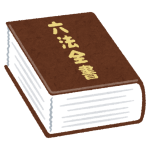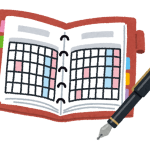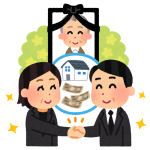当サイトの一部にアフィリエイト広告を含みます。
Contents
1. 家族が知っておきたい「できなくなること」と備えのポイント
最近、母が同じ話を何度もするようになってきて…
このような些細な変化が、実は認知症の始まりかもしれません。
認知症になると、財産管理や契約行為などの大切な判断を下すことが、ご本人では難しくなることがあります。しかし、認知症が進んでからでは、遺言書を作成することも、財産を動かすこともできなくなってしまいます。
この記事では、認知症を発症するとできいなくなることと、ご家族が健康なうちにできる備えについてできる限りわかりやすくまとめました。「まだ大丈夫!」と思っている今こそ、ご家族で一歩踏み出すタイミングかもしれません。
2. 認知症で「できなくなること」家族が気づくべきサイン
認知症は、ある日突然大きな変化をもたらすものではなく、じわりじわりと日常生活に影を落としていきます。ご家族が早い段階で「いつもと違うかも?」と気づいてあげることが、備えへの第一歩です。
以下に、特に注意したい変化の例をご紹介します。
❌ お金の管理が難しくなる
- 公共料金の払い忘れ、クレジットカードの引き落としミスが増える
- ATMの操作に戸惑い、現金の入出金がうまくできない
- 不審な買い物や、詐欺まがいの電話に応じてしまう など
こうした変化を「うっかり」で済ませてしまうと、後に大きなトラブルに発展するおそれがあります。そのため、家計簿を見直す、通帳を一緒に確認する機会を設けられると安心です。
❌ 契約や法律行為ができなくなる
- 遺言書の作成や不動産の売買など、法律行為に必要な判断能力が低下する
- 意思を確認できなくなると、手続きに本人の希望を反映できなくなる
たとえば、認知症が進行した段階で「遺言書を作らなくちゃ」と焦っても後の祭りです。その状態で作成した遺言書は無効と判断される可能性が高く、財産の処分等について、ご自身の意思を反映することはできなくなります。
そのため、ご自身が健康なうちから準備を進めることが大切です。
❌ 日常生活の段取りができなくなる
- 同じ食事を何度も食べようとする、または食事を作り忘れる
- 服装が気候に合っていない
- 約束の時間を間違える
- 外出先で道に迷うことが増える など
離れて暮らしている場合、訪問時の違和感や部屋の様子、冷蔵庫の中身などから小さなサインをキャッチしましょう。
❌ 人づき合いや感情のコントロールが難しくなる
- 怒りっぽくなる
- 会話が嚙み合わなくなる
- 家族の名前を間違える
- 疑り深くなる、被害妄想が激しくなる など
家族と同居している場合、「最近、性格が変わってきた…?」と戸惑うケースもあります。感情の変化は身近な人にも悪影響をもたらすことから、抱え込まず、外部の専門機関を頼るのも選択肢の一つです。
3. 家族が「今からできる備え」
認知症は、進行してしまうと「やっておけばよかった…」と後悔することが多いです。そのため、元気な今だからこそ、家族でできる備えを実行しましょう。
ここでは、早めに取り組みたい5つの方法をご紹介します。
✅ 家族での話し合いを持つ
- もしものときにどうしたいか、本人の意向を確認する
- 介護、財産管理、住まいのことなど、幅広く希望を聞く
話し辛いテーマだからこそ、できる限り穏やかな雰囲気を心がけ、何回かに分けて少しずつ進めましょう。
✅ 任意後見制度・家族信託を検討する
以下を参考に、任意後見制度や家族信託の活用を検討しましょう。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、認知症などで判断能力が低下したときに備え、あらかじめ信頼できる人に「助けをお願いしておく」仕組みをいいます。
- 元気なうちに
👉ご自身で「この人に…!」という後見人を選びます - 公正証書で契約を結ぶ
👉法的に有効な文書とするため、公証役場にて手続きをします - 満を持してボケる
👉医師の診断などを基に、家庭裁判所が後見開始を決定します
🔹 任意後見制度でお願いできること
- 銀行における手続きや支払い代行
- 介護、医療契約の手続き
- 財産管理 など
🔹 家族信託との違い
| 任意後見制度 | 家族信託 | |
|---|---|---|
| 効力発生のタイミング | 判断能力が低下したとき | 自分たちで決められる |
| 家庭裁判所の関与 | あり | なし |
| 権限の範囲 | 法律行為まで○ | 主に財産管理 |
任意後見制度と家族信託は、どちらか一方しか選べないわけではないため、状況に応じ、併用するケースもあります。
🔸任意後見制度はこんな方におすすめ
- 一人暮らしの高齢者
- 親御さんの希望を尊重したいご家族
- 将来的なトラブルを防ぎたい方
弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談することで、ご本人にとって最適な制度を提案してくれます。将来の金銭トラブルや、親族間でのもめごとを防ぐにも有効な手段です。
家族信託とは
家族信託とは、親御さんが元気なうちに「自分の財産をどう使ってほしいか」を決め、信頼できるご家族に対し、財産の管理・運用を託す制度をいいます。
家族信託の活用シーン
- 親御さんの認知症により口座が凍結される前に備えたい
- 実家を売却し、将来の医療・介護費用にあてたい
- きょうだい間でもめないよう財産を分けたい
🏦 どんな財産を託せる?
- 預貯金口座
- 不動産
- 株式、投資信託
- 賃貸収入 など
家族信託では、財産の種類に応じて柔軟に対応することができます。
🧾 家族信託の仕組み
- 親御さん(委託者)が
- 信頼できるお子さんなど(受託者)に
- 財産の管理、運用、処分権限を託し
- 最終的に財産を受け取る人(受益者)を決めておく
⚖️ 任意後見とのちがい
| 家族信託 | 任意後見 | |
|---|---|---|
| 開始時期 | すぐに開始できる | 判断能力が低下したとき |
| 裁判所の関与 | なし | あり |
| 権限の範囲 | 財産の柔軟な活用が可能 | 法律行為の代理ができる |
💡 家族信託はこんな人におすすめ
- 認知症による口座の凍結や、相続トラブルが心配
- 不動産の管理、運用を家族に任せたい
- 柔軟で、自由度の高い備えがほしい
家族信託最大の特徴は、弁護士、司法書士などと一緒に設計することで、「自分たちらしい資産の活かし方」が叶う点です✨
✅ 遺言書やエンディングノートの作成をサポートする
遺言書やエンディングノートなど、本人の意思を有効に残すための対策を講じましょう。はじめから形式にこだわると面倒に感じ、二度と考えようと思えなくなるおそれがあります。そのため、簡単なメモ書きから始めることをお勧めします。
ご家族としては、「どこまで触れていいのか分からない…」と困ることもあるかと思いますが、「書いてみたら?」と提案するより、「一緒にやってみよう」と寄り添うことで始めるきっかけが掴みやすくなります。
✅ 通帳・保険・契約の情報を整理・共有する
- 預金通帳や印鑑の保管場所、ネットバンキングの有無などを共有する
- 保険、年金、サブスク契約などを一覧にしておく
デジタル遺品の整理も重要な備えの一つです。必要に応じ、パスワード管理ツールなどを利用するのもお勧めです。
【関連記事】デジタル遺品の生前整理、相続手続を解説
【関連記事】デジタル遺品の整理と相続方法:スマホ・パソコンの取り扱いガイド
✅ 地域の支援制度や専門家を把握する
- 地域包括支援センターや行政の窓口などを事前に確認する
- 緊急時の連絡先をまとめる
あらかじめ、「いざというとき、どこに相談するか」を知ることで不安を軽減することができます。
【関連リンク】認知症に関する相談先(厚生労働省)
【コラム】親にどう切り出す?
角が立たない5つの声かけヒント
🟡 1. 日常会話にさらっと混ぜる
「この前テレビで相続の特集やっててね…」
→ “話題の延長”なら、構えず聞いてもらいやすい
🟡 2. 教えてもらう姿勢で
「お母さんたちって、将来のことどう考えてる?」
→ “相談”や“質問”の形にすると、親のプライドも守れる
🟡 3. 心配じゃなく“安心”をキーワードに
「みんなが困らないように、準備しといた方が安心かなって」
→ 前向きな理由づけで、親の不安を刺激しない
🟡 4. 希望を聞き出す質問を
「介護が必要になったら、どうしたい?」
→ 選択肢を与える聞き方で、本人の意思を引き出す
🟡 5. 焦らず、きっかけだけでも
「今日はきっかけだけ。またゆっくり話そう」
→ 一度で全部話さなくてOK。小さな一歩から
🔸ワンポイント:
きっかけ作りに「家族信託って知ってる?」「エンディングノートって書いたことある?」など、軽めの言葉から入るのも◎
4. 認知症になってからでは、もう遅い?
「まだ元気だから」「そんなに困っていないから」と思っていても、認知症はある日突然やってきます。…にもかかわらず、そのときになって備えようにも、どうにもならないことが多いのも現実です。
✅ 遺言書を作ろうにも、無効になることがある
遺言書を作成するには、作成者にしっかりとした判断能力が求められます。既に認知症の診断を受けている場合、作成しても無効と判断される可能性があります。
本人の意思を尊重するには、健康なうちに手続きを済ませるのが必須です。
✅ 財産を動かしたくても、凍結されるリスク
認知症が進行した場合、銀行口座や不動産の名義変更ができなくなるケースもあります。こうなると、家族であっても勝手にお金を動かすことができなくなります。
この場合、「介護費用を引き出したいのに、手続きができない…」といったトラブルが考えられます。
✅ 親の希望を聞こうにも、もう話ができない
「延命治療は希望する?」「施設に入るとしたらどこがいい?」
こういったことを本人の言葉で聞ける機会が、ある日ふいに失われる可能性もあります。話せる今が備えられる最後のチャンスになるかもしれません。
✅ 家族が後悔しないために
ご家族の認知症が進んでから、多くのご家族が口にするのが
もっと早く話しておけばよかった…
という後悔の言葉です。こうした備えはご本人のためであると同時に、ご家族の安心のためにも役立つかと思います。
5. まとめ:家族だからこそ、守れる未来があります
認知症は、どなたにとっても他人事ではありません。一度進行しますと、できることが一つずつ減っていきます。
- お金のこと
- 住まいのこと
- 介護のこと
- 人生の最期について
こうしたことをご家族と考え、一緒に準備をできるのは健康なうちです。「まだ大丈夫」は、いとも簡単に「もう手遅れ」に変わります。
ちょっとした会話からでも構いません。今日が一番早い日です。
ご家族の安心のために、この記事を役立てていただければ幸いです。