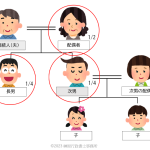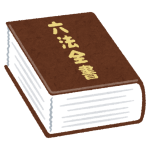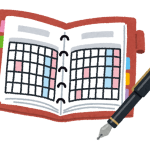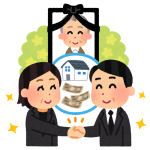当サイトの一部に広告を含みます。
親の老いに気づいたとき、ふと心に浮かぶのが「もしもの時のこと」ではないでしょうか。延命治療、介護、財産、相続…どれも大切なことなのに、いざというときまで手をつけにくいのが現実です。
そこで今回は、「相続開始までに考えておきたい10項目」をわかりやすくまとめました。どれも将来、家族や自分自身が後悔しないための備えです。
最期までその人らしく生ききるために。そして、残される家族の負担や迷いを減らすために。この記事が、あなたの「備え」のきっかけになれば幸いです。
Contents
相続開始までに考えておきたい10項目
-
延命治療の希望
└ どこまで治療する?尊厳死の意思確認 -
介護の方針
└ 自宅 or 施設、費用やサービス確認 -
認知症への備え
└ 任意後見や信頼できる代理人の準備 -
財産の把握
└ 預金・不動産・保険などの一覧化 -
相続の方針
└ 遺言書の有無、家族間での事前共有 -
葬儀・お墓の希望
└ 形式、宗派、誰を呼んでほしいかなど -
デジタル遺品の整理
└ SNS・口座のID・パスワードの管理 -
保険・年金の確認
└ 受取人や請求手続きの流れをチェック -
大切な人との関係整理
└ 伝えたい想いや感謝のことばなど -
家族での情報共有
└ 何かあったときの役割分担・連
🩺 延命治療の希望(終末期医療)
延命治療とは
延命治療とは、本来の回復が見込めない状態で、生命を永らえることを目的とした治療を言います。たとえば、以下が挙げられます。
- 人工呼吸器の装着
- 胃ろう
- 人工透析の継続
- 心肺蘇生
- 強力な点滴や投薬
これらは、本人にとって苦痛を伴う場合もありますが、「生きている状態を維持する」ことが目的となる治療です。
希望を確認する理由
延命治療において、本人の希望が判断を左右します。しかし、判断能力が低下したり、話せない状態になってからでは意思を確認することができません。
そのため、健康なうちから希望を確認しておくことが大切です。
具体的な準備の方法
① リビングウィル(終末期の意思表示)
リビングウィルとは、自分が以下のような状態になった場合、どうしてほしいかを記載する文書をいいます。
- 意識不明になり、戻らない状態のとき
- 回復の見込みがない末期がんなどと診断されたとき
- 認知症の進行で判断ができないとき
たとえば、「回復の見込みがない場合、延命治療は望みません」、「痛みの緩和ケアは望むが、人工呼吸器などは使わないでほしい」といった意思を記載します。
【関連記事】延命治療の拒絶に必要な手続、注意点を解説
② 事前指示書(アドバンス・ディレクティブ)
事前指示書とは、リビングウィルに比べ法的に整えた形式の文書をいいます。医療措置に対し、誰に判断をゆだねるかといった部分まで明記するのが特徴です。
【参考】📄 リビングウィル(終末期医療に関する意思表示書)
以下にテンプレートを添付しますので、必要に応じ、編集してご利用ください、
家族との共有も大切
リビングウィルや事前指示書を作成した場合、それが家族や医療スタッフに伝わらなければ意味がありません。そのため、家族に見せる、またはコピーを渡しておく、かかりつけ医に伝える、介護施設に入る際に提出するなどの対策が必要です。
ポイントまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 延命治療とは | 回復が見込めない状態で生命を維持する医療 |
| なぜ話し合うのか | 本人の意思を尊重し、家族の負担を軽減するため |
| 具体的な準備 | リビングウィル、事前指示書の作成 |
| 家族の関与 | 共有、相談、同意がカギを握る |
🧓 介護が必要になったときの方針とは
親御さんが高齢となり、病気や認知症などで日常生活に支援が必要になった場合に備え、あらかじめ「誰が、どこで、どうやって介護をするか」という介護方針を考えましょう。
検討すべき5つのポイント
① 自宅介護 or 施設介護?
自宅介護と施設介護、どちらが現実的であるかについて、本人の希望を含め検討します。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自宅介護 | 安心して過ごせる | 家族の負担が大きい リフォームが必要な場合も |
| 施設介護 | 24時間体制でサポートを受けられる | 費用が高い 環境が変わることによりストレスを感じる |
② 介護認定(要介護認定)の申請
介護サービスを利用するには、市区町村に申請し、「要介護認定」を受ける必要があります。
- 申請の準備
- 申請
- 認定調査
- 主治医の意見書
- 判定結果
③ ケアマネジャーとの連携
介護認定後、ケアマネジャーがつきます。ケアマネジャーとは、介護の司令塔となる存在で、以下の役割を担います。
- 必要なサービスのプランを作成
- 福祉用具、訪問介護、デイサービスの手配
- 家族や施設との連絡、調整
【関連リンク】サービス利用までの流れ(厚生労働省)
【関連記事】要介護認定から介護予防まで:必要な支援を理解し、スムーズに利用するためのガイド
④ 介護にかかる費用の目安
介護にかかる費用は、在宅か施設を利用するかにより大きく異なります。
| 在宅介護 | 3万~8万円/月 (介護保険自己負担1~3割+交通・食事・訪問サービス代など) |
| 介護付き施設 | 15万~30万円/月 (入居が必要な場合あり) |
⑤ 事前に確認しておきたいこと
介護が始まる前に確認しておきたいことを下表にまとめました。
✅ 介護が始まる前にしておきたい準備チェックリスト
| チェック | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| ☐ | 家族で話し合う | メインで介護に関わるのは誰か どう役割分担するか |
| ☐ | 本人の希望確認 | 自宅介護、または施設の利用を検討 |
| ☐ | 要介護認定の申請 | 認定要件、かかる時間などを確認 |
| ☐ | ケアマネジャーの選定 | 相性のいい人を選び、相談窓口として確保 |
| ☐ | 自宅のバリアフリー化 | 段差、トイレ、手すりの有無など 必要に応じ、リフォームを検討 |
| ☐ | 経済状況の把握 | 親の収支、預貯金、年金の有無 |
| ☐ | 介護サービスへの理解 | 保険で賄える範囲を確認 |
| ☐ | 書類、連絡先の整理 | 預貯金通帳、親族や緊急時の連絡先 その他貴重品の管理 |
| ☐ | 成年後見制度を検討する | 認知症リスクがある場合、財産管理に備える |
ポイントまとめ
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 介護を受ける場所 | 自宅、または施設 本人の希望を確認 |
| 要認定申請 | 要介護認定を早めに申請する |
| ケアプラン | ケアマネジャーと相談しながら作成 |
| かかる費用 | 月額見込みと家族の負担額を試算 |
| 情報収集 | 地域包括支援センターに相談を |
🧠 認知症への備えとは
年齢を重ねると、認知症などのリスクが高まり、判断能力が低下するおそれがあります。この場合、以下のような点で困るかもしれません。
- 預金をおろせなくなる
- 介護サービス、施設への入所手続きができない
- 不動産の名義変更、売却ができない
- 医療同意が必要な場面において、本人の意思を確認できない
こうした事態に備え、健康なうちから備えるべきことがあります。
代表的な制度・手続き 3選
① 任意後見制度(元気なうちに備える)
任意後見制度とは、本人が健康で、判断能力がしっかりしているうちに信頼できる家族や専門家と「任意後見契約」を結び、将来、認知症などで判断能力が落ちた場合に、契約内容に沿い、成年後見人にさまざまな場面で助けを借りることができます。任意後見契約でできることは、以下の通りです。
- 預貯金の管理、支払い代行
- 介護サービスの契約
- 医療同意、施設入所手続き
- 契約行為の代理 など
任意後見制度では、家庭裁判所の関与を受けますので、財産の悪用等のリスクをある程度抑えることができます。
② 家族信託(財産の柔軟な管理)
家族信託とは、自分の財産を特定し、目的を決め、信頼できる家族に対し、管理・運用を託する制度をいいます。成年後見制度と異なり、契約の発効時期に制限がなく、より自由に財産管理を行うことができる一方で、家庭裁判所の介入がなく、チェック機能を担う機関がない点には要注意です。
また、非常に自由度の高い制度ですので、法的な知識を持たなければ事後のトラブルを招くおそれがあります。ですので、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家にご相談いただくと安心です。
【関連記事】家族信託の開始前に検討すべきポイント、必要な手続を解説
③ 成年後見制度(判断力がすでに低下した場合)
任意後見契約と同様、「成年後見制度」の一つですが、こちらの場合は家庭裁判所が成年後見人を選任します。申立人が候補者を挙げることもできますが、ほとんどの場合、弁護士や司法書士が選ばれます。
財産を「守る」制度なので、運用はやや硬直的で融通がきかない印象がありますが、不正の防止には有効な選択肢だと言えます。
ポイントまとめ
| 制度 | 健康なうちにできる? | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 成年後見 (任意後見) | 可能 | 本人の意思で契約 将来への備え | 信頼できる家族に任せたい人 |
| 成年後見制度 (法定後見) | 不可能 | 裁判所が決定 厳格な運用 | 判断能力が著しく低下している人 |
| 家族信託 | 可能 | 財産の柔軟な管理・運用が可能 | 不動産などの資産が多い人 資産に関し、目的がしっかりしている人 |
💰 財産の把握とは
親御さんが亡くなったとき、どこに何があるかわからないと相続手続きが滞り、親族間でトラブルの原因となることがあります。そのため、生前に財産の種類や保安場所、名義変更などを行っておくことをお勧めします。
把握すべき主な財産の種類
把握すべき主な財産の種類は、以下の通りです。
| 分類 | 内容の例 |
|---|---|
| 預貯金 | 金融機関名、支店名、種別、口座番号、通帳の保管場所など |
| 不動産 | 土地、建物の地番や所在地、登記情報、名義人 |
| 保険 | 生命保険や医療保険の加入状況、証券番号、死亡保険金の受取人など |
| 株式・債券 | 証券会社や信託会社、口座番号、銘柄、ネット証券のログイン情報など |
| 年金 | 受給の有無、公的年金、企業年金、個人年金の種類 |
| 貴金属 | 宝石、骨とう品、現物資産、記念硬貨、アンティーク品など |
| デジタル資産 | ネットバンク、仮想通貨、ネット証券のログイン情報 |
| その他 | タンス預金、貸金庫の有無、ゴルフの会員権、コレクションなど |
| 負債 | 借入金、住宅ローン、クレジットの未払金、未納の税金など |
財産目録の作成
できれば生前の内に財産目録を作成しておくと安心です。作成は、WordやExcelなどパソコンで打ち出す方法のほか、手書きでも構いません。
【参考】📄 財産目録(項目)
| 分類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 預貯金 | ○○銀行 ○○支店 普通 0123456 | 通帳は金庫、印鑑は書斎 |
| 不動産 | (自宅) 東京都△△区XX1-2-3 | 土地建物とも本人名義 |
| 生命保険 | ■■生命 終身保険 契約番号ABC123456 | 受取人:長男 証券は引き出し |
| 証券口座 | ○○証券 ネット証券 口座番号ZYX987654 | ログインID、PWは別紙に記入 |
| 負債 | △△銀行 住宅ローン 借入残高約400万円 | 団信加入済み |
管理と注意点
財産管理において、以下に注意しましょう。
- 預貯金通帳、証書類、印鑑の保管場所を明記すること
- できれば複数人に共有できる体制をとること
- 定期的に内容を見直すこと
- 希望する使い道等がある場合は明記すること
🧾 相続の方針とは
親御さんが亡くなった後、親族間でもめることがないように、遺産の分割方法や希望を生前から整理し、共有しましょう。
事前に考えるべき2つの柱
①遺言書の有無と内容の確認
相続において、遺言書の存在はその後の手続きに大きく関わります。なぜなら、有効な遺言書を作成しておくと、原則、その内容に基づき遺産分割が行われるからです。
遺言書の種類
遺言の種類は、以下に分けることができます。
| 種類 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言書 | ・本文をすべて自書(手書き)する必要あり ・法務局に預けることもできる | ・自分で作成する場合、法律上の有効性が保証されず無効になるおそれがある ・自宅保管の場合、変造や改ざんなどのリスクを負う ・死後に家庭裁判所で検認手続きを受ける必要がある ※法務局の保管制度を利用する場合には不要 |
| 公正証書遺言書 | ・公証役場にて、公証人が作成 ・原本は公証役場にて保管される | ・記載額に応じ、費用が異なる ・作成に際し、一定の準備が必要 ・内容を他者に知られる ※公証人や証人には守秘義務があるので漏洩リスクは極めて低いです |
②家族間での話し合い
仮に親御さんが遺言書を作成しない場合、法定相続分に従って分割する、または相続人による話し合いにより分割方法を決定することになります。その際にもめないよう、生前において以下を話し合っておくと安心です。
- 誰に、何を、どれだけ残したいか
- 実家を相続する人から他の兄弟への代償について
- 生前贈与を考えている相手の有無
- 借金、負債の有無
- お墓の管理は誰がするか など
よくあるトラブル例と対策
相続でもめやすい事例と対策について、下表にまとめます。
| 事例 | 対策 |
|---|---|
| 遺言書がない、または見つからない | 公正証書遺言書を作成する、または自筆証書遺言書保管制度を利用し、家族にその旨を知らせておく |
| 遺産が不動産しかない | 不動産の評価方法、分割方法について検討しておく |
| 介護した相続人から不満が出ている | 特別寄与制度の活用、または遺言に希望内容を明記 |
| 生前贈与と相続についての不満 | 贈与した財産がある場合、財産目録や遺言書にその旨と内訳を記載する |
ポイントまとめ:相続の方針は“話す勇気”と“残す仕組み”
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 財産を把握する | 何が、どこにあるか、名義人まで確認し、整理する |
| 遺言書を作成する | 公正証書遺言書が最も安心 付言事項として遺族への思いも記載するとベター |
| 家族で話し合う | トラブルになりやすい点について、事前に確認する |
| 必要に応じて相談する | 行政書士、司法書士、税理士などへの相談 |
⚰️ お墓・葬儀の希望とは
親が亡くなった後、葬儀の方法やお墓のことをどうするかは、残された家族にとって大きな負担になりがちです。
生前に「どんなお見送りをしてほしいか」を本人の意向として聞いておくと、家族の迷い・負担がグッと減ります。
話し合っておくべきポイント一覧
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 宗教、宗派 | 仏教・神道・キリスト教・無宗教 | 菩提寺の有無 |
| 葬儀の規模 | 家族葬・一般葬・直葬など | 費用、希望人数に影響 |
| 式場、場所 | 自宅・斎条・自院・公民館など | 希望場所の有無 |
| 呼んでほしい人 | 親戚・友人・職場の人など | 連絡してほしい人をリスト化 |
| 遺影、音楽など | 希望の写真、好きな曲など | |
| お墓の有無 | 存否と場所 | 永代供養、樹木葬などを含む |
| 納骨先 | お墓・納骨堂・散骨など | 宗教観、家族の意見による |
| 費用負担 | 負担者、予算など | 預金や保険から出す予定も確認 |
| お布施、戒名など | 希望額など | 仏式の場合は重要項となり得る |
| 生前契約の有無 | 終活サービスの契約について |
エンディングノートや希望リストに記録しておくと安心
エンディングノートや遺言書を作成するつもりがない場合、以下の点だけでも確認できると安心です。
- 家族葬で静かに送り出してほしい
- ○○の曲を流してほしい
- お骨は○○霊園の墓に納めてほしい
- お布施は最低限で良し
- ○○さんには必ず知らせてほしい など
畏まる必要はなく、一言だけでもメモを残してもらえると遺族が迷わなくて済みます。
お墓についての選択肢(近年のトレンド)
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 伝統的なお墓 | ・墓石・家名が入っている ・先祖代々管理しているお墓 |
| 永代供養墓 | ・寺院や墓地が管理してくれる ・継承者がいらない |
| 納骨堂 | ・室内型で都心に近くアクセスが良い |
| 樹木葬 | ・自然の中に散骨してもらえる ・宗派にこだわりがない人に人気 |
| 海洋散骨 | ・遺骨を海に撒く ・儀式を行うケースあり |
お子さんがいない場合や、ご家族に迷惑をかけたくないといった理由から、永代供養や樹木葬を選ぶ人が増えています。
ポイントまとめ:本人の“最後の想い”を形にする準備
| やること | 理由 |
|---|---|
| 葬儀の希望を聞く | トラブルや、親族間でのトラブル防止 |
| 読んでほしい人をリストアップ | 親しい人を漏れなく呼ぶことができる |
| お墓の種類、費用を検討 | 予算・信仰・価値観に合った選択ができる |
| 希望をメモやエンディングノートに | 口頭より安心で、証拠となり得る |
💻 デジタル資産とは
デジタル資産とは、パソコンやスマホ、インターネット上のデータやアカウントなどを指します。
代表的なデジタル資産の種類
下表に、代表的なデジタル資産の種類を挙げます。
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| SNS等のアカウント | Facebook、X、Instagram、LINE、TikTokなど |
| メール | Gmail、Yahoo!メール、プロバイダのメールアドレスなど |
| ネットバンキング | ○○銀行オンライン、ゆうちょダイレクトなど |
| キャッシュレス | PayPay、楽天Pay、Suicaモバイルなど |
| ECサイト | Amazon、楽天市場、メルカリ、ヤフオクなど |
| サブスク | Netflix、Spotify、Apple Music、Huluなど |
| 写真・データ保管 | Googleフォト、iCloud、Dropboxなど |
| 暗号資産 | 仮想通貨のウォレット情報 |
| その他 | ブログ、会員制サイト、マッチングアプリなど |
トラブル例と原因
以下に、デジタル資産に関するトラブルの例と原因を挙げます。
| 事例 | 原因 |
|---|---|
| ネット銀行の残高がわからない | ログイン情報を共有していない |
| クレジットカード、サブスクの自動引き落としが止まらない | 契約していること自体を共有していない |
| SNSのアカウントが放置され続けている | 存在自体を把握していない |
| 家族が遺影に使いたい写真がスマホに入っている | パスコートを共有していない |
生前にできるデジタル資産の整理方法
① デジタル資産のリストアップ
生前にできるデジタル資産の整理方法として、使用しているものや、使用状況を書き出す方法が考えられます。
| サービス名 | ID/メールアドレス | PW(ヒント) | 使い道 |
|---|---|---|---|
| Gmail | ○○○@gmail.com | ペットの名前 | メール |
| 楽天銀行 | △△△△ | 引き出しにメモを保管 | ネットバンキング |
| ○○○○ | 誕生日 | SNS |
WordやExcel、紙のノートに記録しておくと○です。
PWについては、ヒントや保管場所を記載する方法が有効です。
②パスワード管理の工夫
パスワードを管理する際は、紙のノートに手書きし、鍵のついた書庫などで保管するほか、パスワード管理アプリ等がお勧めです。
緊急時に開錠できるよう、家族のうちの一人に共有しておくと安心です。
③ 各サービスの死後対応をチェック
故人の死後対応について、各プラットフォームにより対応が異なります。そのため、現在利用しているサービスの死後対応を利用規約等で確認しておくことをお勧めします。
たとえば、Googleの場合は「アカウント無効化管理ツール」という機能があり、○日使わなければ指定した人への通知、または削除など設定することができますほか、Apple ID/iCloudでは、死後アクセスを許可する「レガシーコンタクト(故人の連絡先)」の設定が可能です。
一方で、LINEのようにユーザの死亡を想定していないプラットフォームもあるため、注意が必要です。
家族に向けたメモを残すのも大事
たとえば、「ネット銀行や証券口座があるので、メールを確認してください」、「Googleに写真を保存しているので、ダウンロードして使ってください」、「パソコンのPWは『パスワード管理ノート』に書いてあります」といった文章だけでも、家族の負担がぐっと減ります。
🛡 保険や年金の確認とは
親御さんが亡くなった後、遺族が困るケースの一つに「加入している保険がわからない」「もらっていた年金の種類、振込口座がわからない」という情報不足が含まれます。このような事態を防ぐには、生前の確認が有効です。
確認すべき保険の種類と内容
下表に確認すべき保険の種類と内容の例を挙げます。
| 種類 | チェックポイント | 備考 |
|---|---|---|
| 生命保険 | 保険会社名、証券番号、受取人の氏名 | 死亡時の保険金請求に必要 |
| 医療保険 | 入院、手術の給付対象や期間 | 終末期や介護に |
| がん保険 | 診断一時金、通院給付の有無 | 支払条件が細かいため注意 |
| 個人年金保険 | 支給会年齢、受取方法 | 老後資金、相続対象にも |
| 学資保険 | 満期になっていれば返戻金あり | 孫などへの贈与に影響あり |
ポイント
保険証券の保管場所と引き落とし口座、受取人について確認しましょう。
年金の確認項目
下表に、年金の確認項目についてご紹介します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年金の種類 | 国民年金(自営業など)/ 厚生年金(会社員) |
| 受給状況 | 何歳から・いくら持っているか |
| 受取口座 | どの銀行に振り込まれているか |
| 年金証書 | 年金番号・種類が記載された書類 |
これらは、毎年送られてくる「年金振込通知書」や「年金定期便」で確認することができます。また、年金証書が見つからない場合には、年金事務所に再発行を請求することも可能です。
その他の年金制度
上記のほか、以下の年金制度も考えられます。
- 狭隘年金(公務員・教職員など)
- 企業年金(会社独自の退職後制度)
- 個人年金保険(民間企業による積立型)
親御さんがどの年金制度に加入されているのか、きちんと把握しておくことで緊急時の対応が円滑に進められます。
確認リスト:チェック形式で準備
| チェック | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| ☐ | 生命保険証券の所在 | どこにあるか 誰が管理しているか |
| ☐ | 医療保険・がん保険の契約内容 | 給付条件・給付金額など |
| ☐ | 個人年金の受取状況 | 満期かどうか 受取方法の確認 |
| ☐ | 年金の種類と年金番号 | 国民年金/厚生年金など |
| ☐ | 年金の振込口座 | 取引先金融機関名など |
| ☐ | 保険の受取人の確認 | 古い契約は見直しが必要な場合あり |
トラブル回避のために
トラブル回避のためには、以下に注意しましょう。
- 必要な情報は「エンディングノート」「保健管理リスト」「年金管理メモ」等に残す
- 家族の誰が何を把握しているか、情報の分担と共有を大切に
- 保険会社からの郵便物、メール等を見逃さない
- 保険金には請求期限があるため、早期対応が必要
💞 大切な人との関係整理とは
人生の最期が近づくとき、物理的な整理だけでなく、対人関係の整理も重要です。
「ありがとう」「ごめんね」「本当はこう思っていた」等の気持ちを残しておけるかどうかで、本人はもちろん、ご家族も心の整理がしやすくなります。
人間関係の整理において考えておきたいこと
① 感謝や思いを伝えておきたい人は誰か
- 子ども、配偶者、きょうだい
- 介護をしてくれた家族
- 過去にお世話になった恩人(先生や職場の人など)
- 疎遠になったものの気になっている友人や親せき
口に出すのが難しいことは、お手紙やメモでも十分だと思います。
一行でも気持ちが伝わるものならば、相手にとってはかけがえのない宝物になるのではないでしょうか。
② 縁遠くなった人の連絡先を整理しておく
昔の友人や職場関係の人、親戚の住所録などを整理し、万が一のときに誰に連絡してほしいか、または連絡してほしくない相手について話しておきましょう。
故人が亡くなった際、遺族が「どなたに訃報を知らせればいいのかわらからない」というケースは意外に多いです。そのため、名簿を整理しておくだけでも家族はとても助かるはずです。
手紙やメッセージノートを残すのも有効
メッセージを残したい人、一人一人に手紙を残すのは管理も大変でしょう。そのため、まとめてノートに記録し、保管場所を家族に伝える選択肢もあります。これが“残された人”にとって一番うれしい相続かもしれません
🏠 家族間での情報共有と役割分担とは
親御さんに介護が必要になったときや、万が一のとき、手続きや心の整理をスムーズに進めるには、事前の役割分担が有効です。
主に共有しておくべき情報
下表に、ご家族で共有しておくべき情報の例をまとめました。
| 分野 | 例 |
|---|---|
| 財産関連 | 預貯金通帳、保険、不動産、負債に関する所在と内容 |
| 医療・介護 | かかりつけ医、介護サービス、延命治療の希望 |
| 契約関連 | 年金証書、保険証券、遺言書、印鑑の場所など |
| デジタル資産 | SNS、ネットバンキング、スマホのパスコード |
| 緊急連絡先 | 読んでほしい親戚や友人、菩提寺の情報など |
家族で分担しておくとよい役割例
下表に、ご家族で分担するのが望ましい役割の例をご紹介します。
| 役割 | 担当者(例) | 備考 |
|---|---|---|
| 介護・通院のサポート | 長女 | 一番近くに住んでいる人 |
| 財産の管理、整理 | 次男 | 金融関係に強い、後見人候補 |
| 書類、事務手続き | 三女 | 手続きが得意な人 |
| デジタル資産の整理 | 孫 | PW管理などを担当 |
| 葬儀・お墓の手配 | 長男 | 親族代表として手動 |
| 情報共有係 | 長女 | 各メンバーに最新の情報を共有 |
無理に一人で背負うより、「できる人ができる部分だけ」を引き受けるスタイルがお勧めです。
共有方法のポイント
ご家族で情報を共有する際は、GoogleドライブやLINEグループなどがお勧めです。また、「財産目録」や「連絡帳」は複数人でアクセスできるようにしておくと、一部の家族に負担がかかるのを防ぐことができます。
おわりに
いかがでしたか?親の人生の最終章を穏やかに支えるためには、医療・介護・お金・人間関係といった複数の視点から、事前に整理しておくことが大切です。特にいざという時に慌てないよう「家族間での共有」や「記録に残すこと」は、非常に効果的です。
少しずつでも構いません。できるところから1つずつ、準備を始めてみませんか?
この記事が、あなたやご家族にとって、大切な対話と安心のきっかけになりますように。