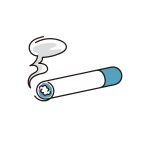当サイトの一部に広告を含みます。
当ページでは、狂犬病に関する罰則と予防接種の時期、接種後に必要な手続きを解説します。
Contents
関連投稿
狂犬病の予防接種は必要?
犬を飼い始めてから知ることも多いかと思います。その中でも特に注意したいのが、以下に掲げる飼い主の義務です。
- 居住する市区町村役所への登録
- 年1回の狂犬病予防接種
- 飼い犬に鑑札、注射済票をつける
いずれも狂犬病予防を目的とする法律に基づくもので、上記の義務に違反した場合、20万円以下の罰金に処される可能性があります(狂犬病予防法 第4条第4項、第27条)。
1.居住する市区町村役所への登録
犬をお迎えした場合、飼い主は居住する市区町村の役所において、「犬の登録(畜犬登録)」手続を行う必要があります。
畜犬登録の目的は、犬に関する責任の所在をはっきりさせることで、飼い主の住所と犬種、予防接種の有無などを把握するのに用いられます。そのため、原則、1頭につき1度で足りますが、転居した場合や犬を譲渡する場合には、その都度登録する必要がある点に注意しましょう。
| 手続き先 | 居住する市区町村の役所 |
| 必要書類 | ✅犬の登録申請書(窓口、または自治体ホームページよりDL) ✅飼い主の身分証明書(氏名、住所、連絡先がわかるもの) ✅犬の情報がわかる書類(名前、生年月日、犬種、毛色、性別など) |
| 登録料 | 自治体により異なりますが、一般的には3,000~3,500円程度です |
| 手続の期限 | 犬を迎えてから30日以内 ※生後90日以内の場合、生後90日を経過した日から30日以内に登録しなければなりません |

2.年1回の狂犬病予防接種
①狂犬病とは
狂犬病とは、ラビウイルス(Rabies virus)により引き起こされるウイルス性疾患で、罹患した動物に咬まれることにより感染します。万が一発症すると致死率は100%で、発症時点で命を落とすことがほぼ確実となる恐ろしい病気です。
狂犬病は人間にも感染するのに対し、発症後の特効薬はありません。しかし、発症前であれば狂犬病ワクチンと免疫グロブリンの投与により予防することが可能です。
致死率の視点で見ますと、致死率最大90%と言われるエボラ熱よりも高いことから、事前の予防や早期発見が不可欠だといえます。
②予防接種の時期
犬の場合、出生後8週~16週頃まで母乳により母乳免疫(「母由来免疫」と呼ばれます。)という抗体を持っています。この免疫は、ワクチンを外敵とみなし攻撃してしまうため、母由来免疫が弱まる頃を見計らい、ワクチン接種を行い免疫を獲得する必要があります。
③予防接種を受けられる場所
狂犬病の予防接種は、行政が実施する集団接種に足を運ぶ、またはかかりつけの動物病院にて受ける方法があります。
集団接種の場合、自治体が指定する日時において、公民館や公園、小中学校等の施設に赴き予防接種を受けることになります。一方、動物病院にて接種を受ける場合には、時期に指定はなく、お好きなときに受けられます。
ただし、毎年1回は必ず受けなければなりませんので、忘れずに受けてましょう。
④かかる費用
狂犬病予防接種を受けるには費用がかかります。具体的な価格については、各自治体や動物病院により異なりますので、事前に確認しましょう。一般的には、3,000~5,000円程度のところが多いようです。
3.飼い犬に鑑札、注射済票をつける
狂犬病予防接種を受けた場合、注射済票が発行されます。この票は、予防接種履歴を示す証明書となりますので、大切に保管しておいて下さい。
仮に、お住まいの自治体以外にある動物病院で予防接種を受けた場合、予防接種に関する証明書が発行されます。これを受け取り、所管の市区町村役所に提出すると注射済票が交付されますので、必ずわんちゃんの首輪やハーネスに装着しましょう。

これらの義務を怠ったらどうなる?
飼い主の義務に違反した場合、罰金の他に以下のデメリットが考えられます。
1.迷子になった場合、見つからない
畜犬登録を行うと、自治体から犬の鑑札が交付されます。この鑑札は、畜犬登録時の内容と連携しているため、飼い犬の身分証になり得ます。
2.ドッグランやペットホテルを利用できない
ドッグランやペットホテルの利用に際し、狂犬病や各種ワクチン接種を受けていることを求められるケースが多いため、受けていない場合は利用させてもらえないおそれがあります。
飼い犬が死亡した場合
飼い犬が亡くなった場合、登録先である市区町村役所、または保健所にて登録抹消手続を行います。この際、犬の鑑札と注射済票を返却しなければなりません。