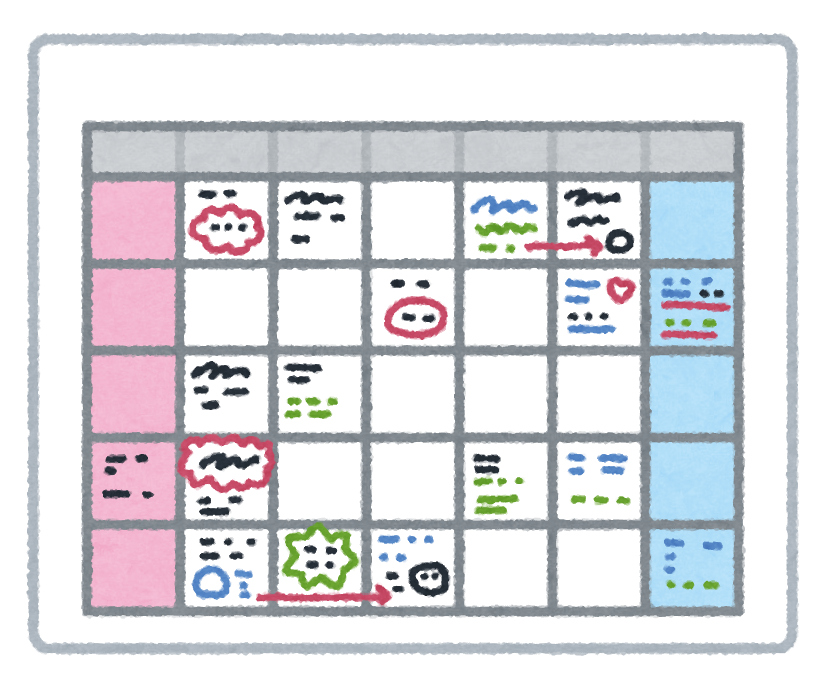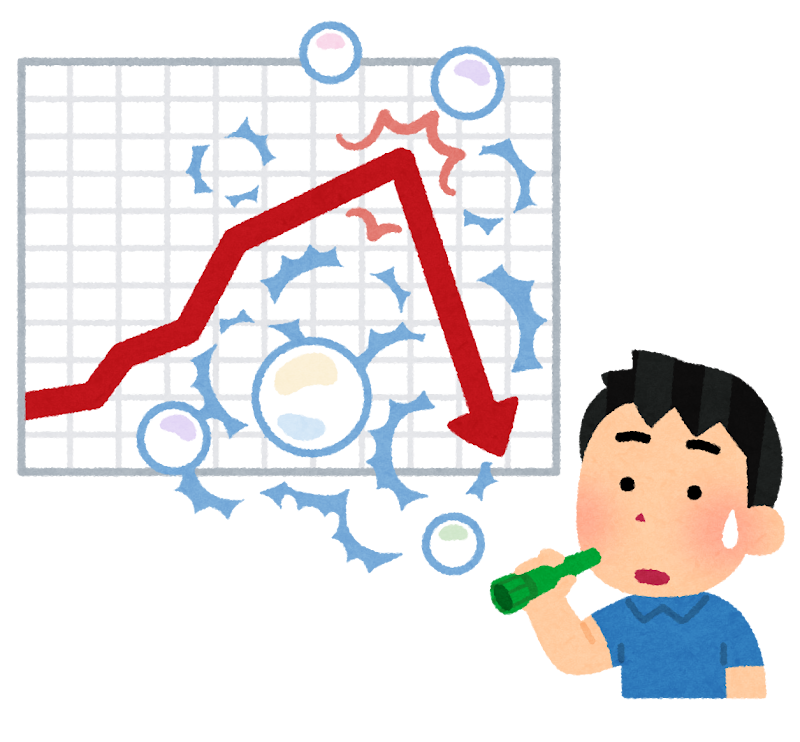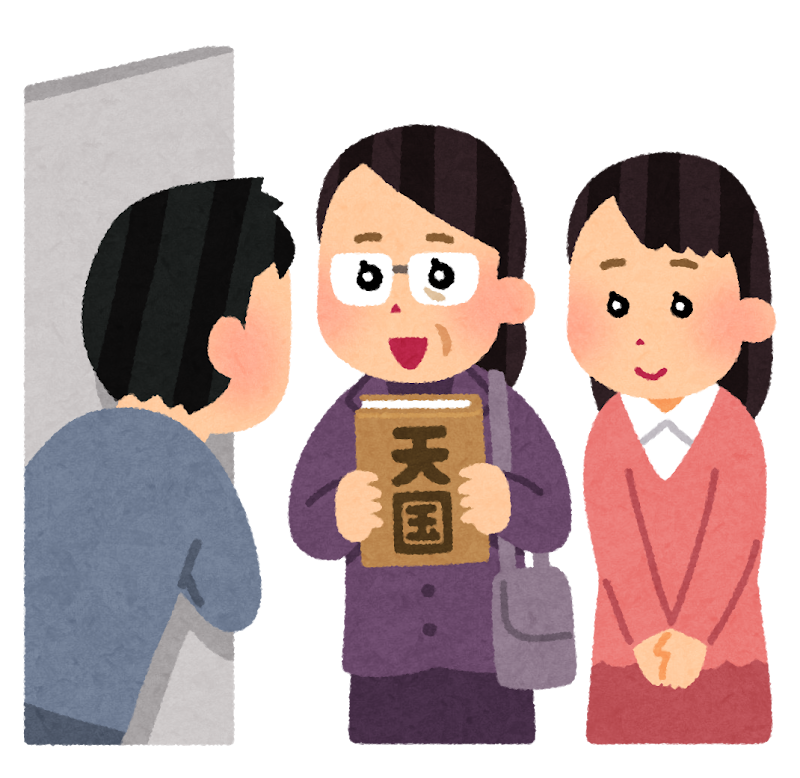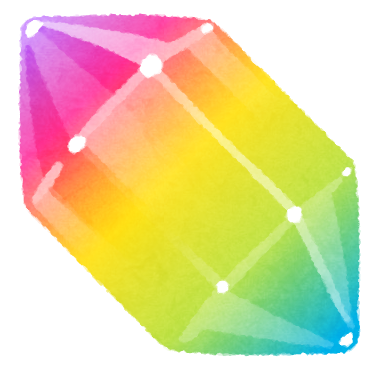当サイトの一部にアフィリエイト広告を含みます。
資格を取るだけでは人生は変わらない理由
資格を取得することは、確かに、新たなキャリアの扉を開くきっかけになる。しかし、それ自体が即座に市場価値を高めるわけではない。資格は、あくまで「土台」に過ぎない。実際、資格を持っているだけでは、企業や市場におけるあなたの価値は限られてしまう。そう。資格=市場価値ではない。
資格+スキル+実績=市場価値
あなたの市場価値を上げるには、資格だけでなく、それを活用するスキルと実績が不可欠だ。たとえば、資格を取っただけで具体的な仕事のスキルがなければ、実際にその資格を活かし、どう成果を出すのか示すことができない。この点、実務経験を積むことで、その資格がどれだけ有効かを証明することとなり、市場での高評価に繋がる。
では、実績を積むためにはどうすればいいのか。
答えは簡単だ。取得した資格を活かせる場に積極的に関わり、常に新しいスキルを習得し続ければいい。資格取得はスタートラインに過ぎない。しかし、その後の努力次第では大きな違いが生まれるのが現実である。
「資格を取るだけで人生が変わる」と思っている人が意外に多いが、実際のところ、資格を持っただけで大きな変化は起きない。
40代にとって本当に役立つ資格の見極め方
40代。正直に言えば、何かをはじめるには遅いと感じることがある。しかし、40代こそ資格取得には有利なタイミングとも考えられる。なぜなら、20代、30代に比べると社会経験や仕事に関する知識・ノウハウを持っており、取得した資格をすぐに活かせるチャンスに恵まれている。
ここで重要なのは、「いまの自分の状態」に合う資格を選ぶことだ。
「資格を取れば稼げる」はウソ?市場価値のある資格とは
資格を取っただけで、「はい、これで稼げます」とはいかない。稼げるかどうかはその資格をどれだけ活かせるかにかかっている。市場価値のある資格とは、単に持っているだけでなく、使い道が多く、より効果が大きなものを指す。
たとえば、資格を取った後の実務経験や、積み上げたスキルでその価値は大きく変動する。ここでの評価基準は、単に、資格の有無だけではない。
キャリアタイプ別!おすすめ資格
1. 会社員のまま年収を上げたい人向け
会社員として働きながら、今より年収を上げたい人には、中小企業診断士や日商簿記がオススメだ。
中小企業診断士は、社内評価を高め、キャリアの選択肢を増やすのに役立つ。経営・経済・財務・マーケティングなど、ビジネスの全体像を理解できる資格で、組織内で昇進につながりやすい。特に、「経営視点を持って動ける人材」は管理職候補として評価されることが多く、年収アップの可能性が高まる。
中小企業診断士が評価されやすい理由👇
- 経営者目線で社内改善ができる → 「業務効率化」「コスト削減」「売上向上」につながる提案で評価が上がる
- 管理職・経営企画・コンサル部門へのキャリアパスが広がる
- 独立の道もある → 会社員として経験を積んだ後、独立してコンサルタントとして稼ぐことも可能
資格を取っただけで給料が上がるわけではなく、診断士の知識を活用し成果を出すことで、昇給やキャリアアップにつなげられるのが強みだ。
日商簿記は、財務・経理の知識を身につけることができる資格で、経理職に限らず、営業・総務・管理職などあらゆる職種で評価される。
日商簿記が年収アップに有利な理由👇
- 財務状況を理解できると、経営判断に関わる仕事ができる → 会社のお金の流れを理解し、「利益を出す戦略」を立てられる人材は評価が高い
- 財務・財務部門でのキャリアアップが可能 → 企業の中核をなす財務部門は、専門知識をもつ人材不足のため、評価されやすい
- 営業職でも「数字に強い人材」は重宝される → 取引先の決算書が読めると交渉力が上がり、高単価の案件を獲得しやすくなる
特に、日商簿記2級以上を取得することで、経理職や管理職候補としてのキャリアが広がり、転職市場でも有利になる。
2. 副業をしたい人向け
副業を始めたいけれど、どんな資格を取ればいいかで迷っている人には、Webライター系の資格や|ファイナンシャルプランナー《FP》がオススメ。
現在、Web上のコンテンツ制作はますます重要視されている。一億人総発信時代ともいわれ、企業や個人にかかわらず情報発信の機会は増え、特に、専門性の高いライティングスキルや、マーケティングと連携したライティングスキルの需要は引き続き高まるだろう。
SEO対策ができるライターは強い
企業が自社サイトやブログを運営する際、Google検索で上位に表示されるには、SEOを意識したコンテンツが不可欠である。そのため、SEOライティングを含む資格を持つことで、無資格のライターと比べ、「Webマーケティング寄りのライター」として高単価案件を狙いやすくなる。
専門分野に強いライターの需要
AIが台頭しているとはいえ、医療・法律・金融・不動産など、専門的な知識が求められる分野では、|人間《ひと》の需要はまだ高い。特に、「一次情報(実体験を伴う記事)」や「専門家監修」の記事が求められることから、こうした分野に特化したライターがAIに置き換えられるとは考えにくい。
自分の知識を活かして副収入を得る
資格を取ることで、自分が得意な分野を活かした執筆が可能となる。たとえば、FPは金融メディア、医療系資格は健康関連などの形で、特定ジャンルに強いライターとしての地位を確立しやすくなる。
総合的に見て、ライティングは場所を選ばず、副業として始めやすいことも魅力である。スキルを磨くことで本業以上に稼ぐことも可能なため、検討の余地はあるだろう。
FPの魅力は、副業でも収益化しやすいことだ。お金に関わる知識を持つと、個人や企業のアドバイザーとして活躍でき、副業として成立しやすい。
お金の知識は一生モノで、需要高
資産形成や副業、投資、節税、年金など、FP試験突破に必要なこれらの知識は、老若男女問わず求められているスキルでもある。特に、40代以降において、「老後資金が不安」「投資を始めたい」「税金対策を知りたい」といった声も増え、FPの知識を活かした相談対応が考えられる。
ブログ・YouTube・SNSを活用して収益化しやすい
FP資格を持っていると、ブログやYouTubeでお金の知識を発信し、アフィリエイトやコンサルティングによる収益化の道もある。「〇〇証券の口座開設」「おすすめの積立NISA」など、お金に関わるコンテンツは広告単価が高く、ライティングスキルと組み合わせることでより副収入を得やすくなる。
副業コンサル・相談業務にもつなげられる
FPとして、個人相談や会社員向けのマネーセミナーの開催、企業の福利厚生プランのアドバイザーなど、収入源を増やす手段が豊富だ。特に、SNSで情報発信を続けることで信頼を得ることができれば、副業の依頼が自然と舞い込むようになるだろう。
3. 独立を考えている人向け
独立を目指す人には、社労士や行政書士などの士業資格がピッタリだ。
いずれも企業や個人事業主を相手に専門的なサポートを提供する仕事で、資格を活かして事務所を構え、自由に働く道が開ける。
社労士(社会保険労務士):企業の労務管理を支える専門家
社労士(社会保険労務士)は、企業の労務管理や社会保険手続きを専門とする国家資格である。特に、人事・労務の知識が求められ、企業にとって欠かせない存在になりつつある。
企業の労務リスク管理の需要が高い
近年の働き方改革や労務トラブル、未払い残業問題など、これまで以上に適切な労務管理が求められる。そのため、社労士に相談する企業が増えており、独立後の案件獲得経路を考えやすい。
ストック型ビジネスができる(顧問契約)
社労士は、企業との顧問契約を通し、毎月の労務管理や手続きを代行することで安定した収益を確保できる可能性がある。単発の仕事に限らず、継続収入が見込めるのは大きな強みだ。
個人向けにも需要あり
社労士は、年金相談や助成金の申請、働き方のアドバイスなど、企業だけでなく個人向けにも業務の幅を広げることができる。特に、副業やフリーランスが増えている昨今において、個人向けの社労士サービスも伸びている。
行政書士は、官公庁に提出する書類作成や手続き代行を得意とする国家資格である。特に、許認可業務に強いため、企業や個人事業主にとって頼もしい存在だ。
会社設立・許認可の手続き需要が安定
起業ブームや副業の解禁により、法人を設立する人が増加傾向にある。その際、必要な書類の作成や許認可の取得に関わる手続きをサポートする仕事は、今後も安定的な需要が見込まれる。
扱う業務の幅が広く、独立後に専門分野を選べる
たとえば、「外国人のビザ申請」「遺言・相続手続き」など、得意な分野を持つと他の行政書士との差別化が容易となる。
自由な働き方がしやすい
行政書士業務の多くは、PCとインターネット環境が整っていれば行うことができ、開業コスト・運営コストともに比較的抑えられ、在宅での業務も可能だ。そのため、自分のペースで働けるのも魅力だといえる。
このように、あなたが望むキャリアにより、役立つ資格は全く異なる。副業を始めたいが、今の自分がどの資格を選べばいいのかで迷うときは、希望する働き方から逆算し、必要資格を見極めるといいだろう。
時間・お金をムダにしない資格学習法
資格学習で大切なことは、時間や費用を無駄にせず、いかに効率よく学べる方法を選べるかだ。たとえば、出題範囲を一気に網羅するのは無謀だといえる。なぜなら、時間がかかるうえにモチベーションの維持が困難だからだ。この点、優先順位をつけ、段階的な学習がお勧め。
計画的な学習を
資格学習の進捗管理には、月、週単位の目標設定が有効である。計画の策定により無駄な労力を削減し、集中力を高められる。
反復学習がおすすめ
資格学習に対応するには、1度なぞっただけでは不十分。暗記ばかり意識するのではなく、短期で高回転の反復学習を行い、思い出す能力を養ってほしい。
挫折しない環境づくり
資格学習で挫折する人の多くは、モチベーションの維持が下手だ。この点について、学習する環境を整え、維持を可能にする方法が考えられる。
学習場所の工夫
集中力をあげるには、学習場所を意識すると良い。自宅やカフェ、図書館など、あなたが落ち着き、集中しやすい場所を知ろう。
誘惑の徹底排除
SNSやテレビ、漫画、LINEなどの誘惑から逃れるため、集中できる環境を意図的につくる。学習時にはスマホ等のデバイスを別室で管理する、書斎に不要なものを置かないなど、意思に頼るのではなく、強制的に学習するしかない空間をつくるのが近道である。
仕事・家事と両立するための時間管理術
40代の多くは、仕事に家事、さらにプライベートも忙しく、学習時間の確保が難しいようだ。しかし、|時間管理《タイムマネジメント》さえうまくできれば、効率よく学習することが可能である。
隙間時間の活用
通勤時間やランチタイムなど、短時間でも積極的に活用しよう。より賢く活用するには、資格関連のスマホアプリや音声教材を導入する方法が有効だ。
優先順位をつける
タスクが多いときほど優先順位をつけ、集中する時間を確保しよう。「時間があれば」と考えるより、あらかじめ学習時間をスケジューリングすることで、他とのバランスがとりやすい。
「毎日やる」では続かない。成功者の学習ルールとは
資格学習を続けるには、毎日やるでは続かない。なぜなら、仕事や家事で疲れる日もあるだろうし、忙しい毎日に追われ、緊急度の低い資格学習は後回しになることも多いものだ。そこで、成功者が実践する学習ルールを紹介したい。
「毎日やる」を「週〇回やる」に
理想は、毎日休むことなく定刻に学習することだが、現実には困難を極める。そのため、「週〇回は必ず学習する」という形にし、柔軟に進めるのがお勧め。
目標は刻む
学習内容や時間設定に無理がある場合、簡単に挫折するのが人間である。この点、「1日30分」や「1日〇問」というように、目標を細かく分けて設定することで達成感を得やすく、成功体験としてモチベーションアップにつなげやすくなる。
独学?スクール?コスパの良い学習法の選び方
資格学習は、独学とオンラインや通学などのスクールとに大別されるが、それぞれにメリット・デメリットが存在する。どちらが良い悪いの話ではなく、予算や希望の学習スタイルにより最善の選択をしてほしい。
独学の場合
独学最大のメリットは、自分のペースで学べることだ。一方で、教材選びや学習計画に迷う可能性があるため、前もって計画を策定しておくと安心である。費用が低く抑えられるのもポイントだが、とにかくトライ&エラーとなることから、総合的に見ると高くなる可能性もある。
スクールの場合
スクールの場合、カリキュラムやサポート体制が充実しているところが多く、効率よく体系的に学ぶことができる一方で、費用や時間が固定され、融通がきかないデメリットがある。自己管理が苦手な人やモチベーションの維持が困難な場合、学習環境を整えられない事情がある場合、特にお勧め。
コスパを考える場合、自己管理が得意なら独学も十分に有効だろう。しかし、わからない部分が多く、計画の策定やモチベーション維持への不安が大きい場合、結果的にスクールの方が効率よく進められる可能性が高い。
このように、資格学習の成功には、計画的な学習と環境の整備、モチベーションを維持する方法を見つける必要がある。多忙な日常にあっても工夫次第で学習時間は確保できる。はじめは無謀に思えても、コツコツ積み重ね、適宜修正を加えながらやっていこう。
資格取得後のキャリア戦略
資格を取った後、あなたがどう動くかにより、その先のキャリアは大きく変わる。最も重要なことは、資格の取得を「スタートライン」と捉え、その後の実務経験やスキルを積むこと。資格を持っているだけで仕事が増えるわけではないし、実績がなければ持っている意味そのものが薄れてしまう。
キャリア戦略として、以下のステップを意識してほしい。
1.実務経験を積む
資格取得後にやるべきことは、実務経験を積むことだ。特に、資格に関わる分野での実務を行う必要がある。たとえば、日商簿記試験に合格した場合、経理業務を経験しなくては資格の信頼性を高めることはできない。
2.実績を積む
積極的に資格を活かせる仕事を探し、実績を作ろう。実勢を積むことで資格への評価も向上し、転職や昇進に際し、大きなアドバンテージとなる。
3.ネットワーキング
資格の取得後において、同じ分野で活躍する人と交流を深めよう。業界内にネットワークを築くことにより、新たなチャンスや情報にアクセスできるようになる。
取った資格を「生かせる人」と「ムダにする人」の違い
資格を取っただけで、人生が変わることはない。むしろ、資格を取ったのに何も変わらなかったと嘆く人が多い。
では、資格を生かせる人と無駄にする人との違いは何なのか。
1. 目的は明確か
生かせる人 → 「資格を何に使うか」が決まっている
- 「この資格を取ったら、転職活動でアピールしよう」
- 「独立したいから、この資格を使って仕事を獲得する」
- 「今の仕事で評価を上げるために、資格を武器にする」
資格を生かせる人の場合、遅くとも資格を取る時点において、「この資格をどう使うか」を具体的に考えている。
ムダにする人 → なんとなく取って満足する
- 「とりあえず資格を取れば、なんとかなるでしょ」
- 「資格を取ったら転職できるはず!」
- 「勉強したから、あとはいい仕事が来るのを待とう」
資格を無駄にする人は、資格の取得自体が目的となっており、その後に行動することはなく、何ら変化が起きることはない。
2. 資格+〇〇があるか
生かせる人 → 「資格+スキル+実績」を意識している
繰り返すが、資格の取得はあくまでスタートラインである。その資格で稼ぐには、「資格+実務経験」や「資格+スキル」など、何か+となるものが存在する人の方が圧倒的優位である。
たとえば、FPの場合は「お金の知識+資産運用の経験」を発信することで信頼の獲得、Webライターの場合、「資格+ポートフォリオ作成」で実績を積む、社労士の場合、企業の労務相談に積極的にかかわり、やはり実績を積む方法が考えられる。
資格を持っているだけで満足するのではなく、+α の強みを作り、のばすことができる人こそ、資格を最大限に活用できる。
ムダにする人 → 資格だけで評価されると思っている
- 「資格を取ったんだから、企業が採用してくれるはず」
- 「資格があるんだから、仕事が勝手に来るはず」
資格を無駄にする人は、取得した資格そのものが評価対象となり、自然に信頼を得られると思い込んでいるケースが非常に多い。しかし、実務経験やスキルのある同資格保有者と比較された場合、果たして、このような人が選ばれる可能性はどれほどだろうか。おそらく、ゼロに近いはずだ。
このことから、資格だけでなく実務経験やスキルがなければ、市場価値は上がるどころか下がるリスクすら含んでいることを肝に銘じたい。
3. 資格を活かすために「行動」しているか
生かせる人 → 資格を活かすための行動を起こす
- 実務経験を積む(副業、ボランティアでもOK)
- SNSやブログで発信する(「◯◯資格の勉強中」→「◯◯の仕事をしています」へ)
- 転職・独立に向けた営業をする(人脈を作る、ポートフォリオを見せる)
資格を生かせる人は、どうやってその資格を武器にするかを意識し、実際に行動している。
ムダにする人 → 何もせず「待機」状態
- 資格を取っただけで何もせず、チャンスを待っている
- 転職サイトに登録しただけで、自分から動かない
- 仕事を選びすぎて、何も経験が積めない
資格を無駄にする人は、どのような資格であっても行動に移さない。資格は使わなければ価値を発揮できず、宝の持ち腐れとなりかねない。
資格を活かすために今すぐやるべきこと(実務経験、SNS活用)
資格を取った後、すぐにでも始められる具体的なステップとして、実務経験を積むこと、SNSを活用した専門性のアピールなどが挙げられる。
1.実務経験を積む
資格を取得しただけで市場価値は上がらない。そのため、仕事でその資格を使う場面を見つける、またはフリーランスとして実績を積むことも方法の一つだ。また、ボランティアやインターンシップ等で実務経験を得られる場合もあるので、自分の脳内だけで終わらせないようにしよう。
2.SNSを活用した専門性のアピール
資格を取得した後、SNS等を介して専門性をアピールすると効果的だ。たとえば、XやInstagram、Facebook等で資格に関する情報をシェアする、または自分がどのように資格を活かしているかを発信すると、同じ分野で働く人たちの目に止まりやすく、横のつながりを持つことができたり、仕事の依頼が届く可能性がある。
これらのアクションを通じ、資格の価値を最大化し、次のステップへと進む足掛かりを作ろう。
資格を取った後、あなたがどう行動するかでキャリアの成功は大きく左右される。資格取得は単なるスタートに過ぎず、活用法が最重要であることを忘れないよう行動しよう。