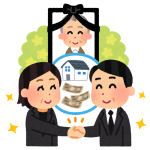当サイトの一部に広告を含みます。
当ページでは、生前贈与の非課税枠と注意点、非課税枠が適用されない場合に考えられる対策を解説します。
生前贈与とは
生前贈与とは、あげる側が生きているうちに自分の財産を他人に無償で譲ることをいいます。亡くなったときに行われる「相続」とは異なり、「生きている間に」譲るのがポイントです。
1.生前贈与の対象
生前贈与の対象となる財産について、その種類や金額に制限はありません。そのため、現金預貯金や不動産、株式、宝石・貴金属類などの動産まで含まれます。
2.生前贈与と相続の違い
相続の場合、故人が亡くなってから財産が移転することとなりますが、遺言書が作成されていない場合には、法律に従った割合にて分割・承継されることになります。
いっぽう、生前贈与の場合には、贈与者が生きている間に自分の意思により財産を譲ることができる点が大きく異なります。
もらう側が支払う税金の種類も、相続は「相続税」、生前贈与は「贈与税」と異なる点に注意しましょう。
生前贈与のルール
人が亡くなり、相続が発生した場合、一定の要件を満たす「亡くなる前に贈与した財産」も相続税の対象に加算されることがあります。
1.加算されるケース
相続税に加算されるのは、以下に該当する場合です。
- 故人から相続、遺贈、相続時精算課税による贈与等で財産を受け取った人
- 生前に、故人から暦年贈与を受けていた人
①暦年贈与
暦年贈与とは、毎年1月1日~12月31日までの1年間における贈与の総額が110万円までを非課税とする制度です。そのため、親から100万円/年を受け取ったときには贈与税がかかりませんが、200万円/年を受け取った場合には、90万円(200万ー110万円=90万円)に贈与税が課せられることになります。
②相続時精算課税
相続時精算課税とは、類型2,500万円までの贈与は非課税となるいっぽうで、免除された税額は相続時にまとめて清算し、相続税に反映される制度です。この制度を利用できるのは、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫を対象に贈与が行われる場合に限られます。
たとえば、60歳の父が30歳の息子に対し、1,500万円の不動産を贈与した場合。贈与時には税金がかかりませんが、父の死亡後、1,500万円を相続財産として計算に組み込むこととなります。
【参考】暦年贈与と相続時精算課税の比較
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 毎年110万円 | トータル2,500万円 |
| 適用対象 | 誰からでもOK | 60歳以上の親や祖父母から子や孫への贈与に限る |
| 課税時期 | 毎年課税 | 相続時にまとめて精算 |
| 制度の変更 | 戻せる | 一度選ぶと戻せない |
| 向いているケース | 少額ずつ長期に渡って贈与する場合 | 不動産や株式などを一括贈与する場合 |
相続時精算課税制度を選択した場合でも、年間110万円までの基礎控除が適用されるほか、基礎控除部分については、相続財産に加算されません👌
2.対象にならない人
反対に、以下に該当する人は加算の対象となりません。
- 相続も遺贈も受けていない人
- もらったのが「教育資金」や「結婚子育て資金」の残金だった人
- 相続時精算課税だけで財産をもらっていた人
3,加算対象期間
加算対象期間とは、故人の生前において行われた贈与について、どの期間まで加算するかを定めたものです。
| 故人の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| ~令和6年12月31日 | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日までの間 |
| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内 |
相続税の計算時における生前贈与の扱い
1.生前贈与と相続税の加算
故人が亡くなる前に行った110万円以下の贈与であっても、加算対象期間に行われた贈与財産の価額は、相続税の計算に加える必要があります。
しかし、贈与時点で納めた贈与税がある場合には、相続税の計算時には控除されることとなります。ここで引かれるのは、贈与税額です。
要するに、加算されるとすれば「贈与財産の金額」、引かれるのは「それに対して納めた贈与税」のぶんということですね。
2.加算対象となる生前贈与の範囲
加算対象となるのは、以下に該当するものです。
- 故人からの贈与で、相続開始前7年以内に贈与されたもの
- 贈与税の課税・非課税にかかわらず、すべて加算
①110万円以下の贈与も対象
②死亡した年の贈与も対象
3.贈与税が非課税になる場合
故人から生前に贈与された財産のうち、次の財産は相続財産に加算する必要はありません。
- 配偶者控除の適用範囲(最大2,000万円まで)
- 住宅取得資金の非課税贈与(一定要件あり)
- 教育資金の一括贈与(非課税で管理されているもの)
- 結婚・子育て資金の一括贈与(非課税で管理されているもの))
ただし、これらに該当する場合でも「使いきれずに残った金額」について、贈与者が亡くなったときに相続財産として扱われる可能性があります。
1.配偶者控除の適用範囲
夫婦間において、自宅または自宅となる不動産を取得する目的で金銭の贈与があった場合、基礎控除額110万円に加え、最大2,000万円まで控除を受けることができます。
この制度を「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(以下、「配偶者控除」と記載します)」といいます。
①配偶者控除の適用を受けるための要件
配偶者控除の適用を受けるには、下記を満たす必要があります。
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後にされた贈与であること
- 配偶者から贈与された財産が居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産、または贈与された金銭で取得した居住用不動産に受贈者が住んでいて、その後も引き続き住む見込みがあること
②対象者・対象物
対象となるのは、婚姻期間20年以上の夫婦であり、内縁者は含まれない点に注意しましょう。
また、対象となるのは「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」です。
端的に言えば、自宅をそのままもらうか、自宅となる不動産の購入資金を贈与された場合が該当します。
③必要な手続・書類
配偶者控除の適用を受けるには、下記の書類を添付し、確定申告をしなければなりません。
-
財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本または抄本
-
財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
-
居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
2.住宅取得等資金を贈与した場合
令和4年1月1日~令和8年12月31日までの期間中に、父母または祖父母等の直系尊属から自宅等の新築、取得、または増改築等を目的とした金銭の贈与があった場合、一定要件を満たすことで、贈与税が非課税となります。
①対象者・対象物
当該贈与について、受贈者が下記の要件を満たすと非課税特例が受けられます。
-
贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
-
贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること
-
贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
※新築等をする住宅用家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下 -
平成21年分~令和3年分までにおいて、贈与税申告による「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
-
自分の配偶者・親族等、一定の特別な関係がある人から取得した住宅用家屋ではないこと、又はこれらの人との請負契約等により新築・増改築等をしたものでないこと
-
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
-
贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
※受贈者が一時居住者、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除く
②住宅用の家屋等の要件
「住宅用の家屋の新築」とは、新築する不動産の敷地に含まれる土地等または新築に先行し、敷地となる土地等の取得を指します。
「住宅用の家屋の取得または増改築等」とは、住宅の取得または増改築等と共に取得する土地等を指します。
いずれも、対象となる住宅用の家屋は日本国内のあるものでなければならず、下記を満たす必要があります。
| 新築または取得の場合 | イ | 下記のいずれも満たすこと ①新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下 ※対象不動産がマンション等のの区分所有建物の場合、その専有部分の床面積 ②その家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること |
| ロ | 取得した住宅が下記のいずれかに該当すること ①建築後使用されたことのない住宅用の家屋 ②建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの ③建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、一定の書類により「地震に対する安全性に係る基準に適合するもの」と証明されたもの ④建築から使用されたことのある住宅用の家屋のうち、上記②および③のいずれにも該当しないもので、取得日までの間に、同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うために都道府県知事等に申請し、かつ、その耐震改修により贈与を受けた翌年3月15日までに耐震基準に適合することを一定の証明書等により証明されたもの | |
| 増改築等の場合の要件 | イ | 下記のいずれも満たすもの ①増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下 ※マンション等の「区分所有建物」の場合、その専有部分の床面積 ②その家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が、受贈者の居住の用に供されること |
| ロ | 自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われた増改築等に係る工事で、一定の工事に該当することにつき、「確認済証の写し」「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」等の書類により証明されたもの | |
| ハ | 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること また、増改築等の工事に要した費用の額の1/2以上を、自己の居住の用に供する部分の工事に要したこと |
③非課税限度額
当制度の適用を受ける場合、下記が非課税限度額となります。
| 区分 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 省エネ等住宅の場合 | 1,000万円まで/受贈者1人につき |
| それ以外の住宅の場合 | 500万円まで |
省エネ等住宅とは、下記のいずれかに該当する住宅用家屋であり、「住宅性能証明書」等の一定書類を添付して証明する必要があります。
-
断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること
-
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること
-
高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
④必要な手続
非課税特例の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に、贈与の申告書に戸籍謄本、新築・取得等に係る書類等を添付し、納税地の所轄税務署に届出る必要があります。
3.教育資金を一括贈与した場合
令和8年3月31日までの間に、教育資金に充てる目的で、父母または祖父母等の直系尊属から30歳未満の子または孫等に一括贈与をした場合、一定要件を満たすことで、最大1,500万円まで贈与税が非課税となります。
①対象者・対象物
当 該特例の適用を受けるには、下記の要件を満たす必要があります。
| 受贈者 | ①30歳未満の子供もしくは孫であること ②前年の所得が1,000万円を超えないこと |
| 贈与者 | 直系尊属であること |
対象となる費用は、下記の通りです。
- 入学金
- 学用品購入費
- 授業料、保育料、学習塾の月謝など
- 給食費
- 施設設備費
- 検定料、受験料など
- 修学旅行費
- 教材等の物品購入費
- 定期券など旅費交通費
- 留学にかかる交通費、その他費用など
②必要な手続
当該特例を受けるには、下記の手続が必要です。
- 贈与者、受贈者間で贈与契約を締結する
- 受贈者名義の教育資金口座を開設
- 口座を開設した金融機関に対し、教育資金非課税申告書を提出
- 贈与者が口座に教育資金を入金する
税務署に非課税申告書を提出するのは金融機関なので、当事者は順序をしっかり守ることに気を配る必要があります。
③教育資金非課税特例を受ける際の注意点
当該特例を受ける場合、下記に注意しましょう。
- 受贈者が30歳になった時点で未使用分に対し、贈与税が課される
- 当該特例の適用を受けるには立替払い、請求手続が必要
- 特例適用中に贈与者が死亡した場合、未使用分に対し相続税が課される
4.結婚・子育て資金を贈与した場合
令和7年3月31日までに、父母または祖父母等の直系尊属から、結婚・子育ての資金として、18歳以上50歳未満の人が贈与を受けた場合、受贈者1人について最大1000万円までの贈与税が非課税となります。
①対象者
当該特例の適用を受けられるのは、贈与時点において18歳以上50歳未満であり、受贈の前年の所得が1000万円以内でなければなりません。
具体的には、父母、祖父母等の直系尊属からの贈与が対象であり、曾祖父母や養父母まで含みます。
②対象となる費用
当制度の対象費用は、下記の通りです。
| 区分 | 内容 | 上限額 |
|---|---|---|
| (1)結婚に係るもの | ①挙式費用、衣装代等の費用 ②家賃、敷金等の新居費用 ③結婚に伴う転居費用など | 300万円まで |
| (2)妊娠、出産、育児に係るもの | ①不妊治療に要する費用 ②妊婦健診にかかる費用 ③分娩、産後ケアにかかる費用 ④子の医療費、保育料など | (1)との合計額1,000万円まで |
③必要な手続き
当制度の適用を受けるには、下記の手続きが必要です。
- 結婚・子育て資金用の口座を開設
- 金融機関に結婚・子育て資金非課税申告書を提出
- 贈与者から当口座に入金
- 結婚・子育て資金口座から払い出し
贈与税の申告・納税方法
贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に申告・納付しなければなりません。
申告先は、受贈者の住所地を管轄する税務署です。
1.申告方法
増税の申告は、下記のいずれかの方法で行うことができます。
- 税務署の窓口に書類を提出
- 必要書類を税務署に郵送する
- e-Taxを利用し、オンライン申告
2.必要な書類
贈与税の申告時には、下記の書類が必要です。
| 贈与税申告書第一表 | 贈与者、受贈者に関する情報 贈与された財産の内容(種類、細目、利用区分、銘柄等) 財産を取得した年月日、財産の価額 |
| 贈与税申告書第一表の二 | 自宅の新築等に関する資金を援助してもらった場合、住宅資金非課税限度額に下記いずれかを記入 ・対象となる住宅が省エネ等住宅の場合は1,000万円 ・一般住宅の場合は500万円 |
| 贈与税申告書第二表 | 相続時精算課税を選択した場合に記入 |
上記の他、下記の添付書類が必要です。
| 共通 | ①本人確認書類 ②贈与財産の価額を証明する書類 |
| 配偶者控除の特例を受ける場合 | ①受贈者の戸籍謄本(抄本)、戸籍の附票の写し ②対象の居住用不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) ※申告書に不動産番号を記入する場合には添付不要 |
| 住宅取得資金の非課税特例を受ける場合 | ①受贈者の戸籍謄本など ②受贈者の源泉徴収票など合計所得金額が確認できる書類 ※所得税の確定申告書を提出した場合は不要 ③対象となる住宅の工事請負契約書の写し、または売買契約書の写しなど(契約の相手方が確認できるもの) ④その他住宅に関する所定の書類 |
| 相続時精算課税を選択した場合 | ①相続時精算課税選択届出書 ②受贈者の戸籍謄本など ③対象となる住宅の工事請負契約書の写し、売買契約書の写し、対象不動産の登記事項証明書など(契約の相手方が確認できるもの) ④その他住宅に関する所定の書類 |
生前贈与を行う際の注意点
生前贈与を行う場合、下記に注意しましょう。
- 併用できない制度・特例がある
- 生前贈与は当事者双方の合意がなければ成立しない
- 相続人の遺留分に配慮する
- 死亡後、一定期間内の生前贈与は持ち戻しの対象となる
1.併用できない制度・特例がある
適用を受けたい制度や特例が複数ある場合、併用できないものが存在するため、最も節税効果の高い方法を比較検討しておくと安心です。
自分で計算するのが難しい場合、ざっくりとした財産額を提示することで税理士から自分に合うであろうアドバイスを得ることができます。あまりざっくり過ぎると明後日の方向に転がりかねないので、開示する際は慎重に参りましょう。
2.生前贈与は当事者双方の合意がなければ成立しない
生前贈与を行う場合、口頭で約束を取り付けても構いませんが、後発的なトラブルを避けるためには、書面の作成をオススメします。
特に注意したいのが、一方的に贈与者が受贈者のためにと金銭を用意している場合です。
子や孫の名義で預貯金口座を用意していても、本人との合意がなければ生前贈与に含まれず、贈与者死亡時には相続税がかかる点に注意しましょう。
3.相続人の遺留分に配慮する
一部の相続人にのみ生前贈与を行う場合、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
この場合、侵害された相続人は受贈者に対し、遺留分侵害額請求を行うことができ、結果的に、生前贈与を行った意味がなくなるリスクがあります。
また、このような事象が起こった場合、親族内の関係に亀裂が入ることも十分考えられますので、生前贈与を行う場合には遺留分に気を付けましょう。
【関連記事】遺留分をもつ相続人と割合、相続時の注意点を解説
4.死亡後、一定期間内の生前贈与は持ち戻しの対象となる
相続開始の7年前までに行われた生前贈与について、贈与された財産は相続税の課税対象に含まれます。
このため、一部の相続人にのみ生前贈与が行われていれば、当該相続人(受贈者)の相続分から贈与財産が引かれた金額を相続することになります。
ただ、この規定の対象者は法定相続人が受贈者の場合に限られるので、節税効果を最大化するには、相続人以外への生前贈与を検討するのも効果的です。
第三者への生前贈与でも、基礎控除額を超えれば課税対象となる点に注意です。
生前贈与の非課税枠、注意点まとめ
当ページでは、生前贈与の非課税枠と注意点を解説しました。