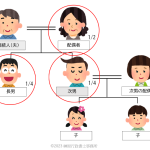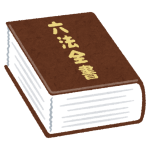当サイトの一部に広告を含みます。
相続税は、故人の財産を受け継いだ際に、相続人が納める税金です。相続税の計算方法は少し複雑で、課税対象となる財産や控除額、加算対象となる贈与財産など、考慮すべきポイントが多くあります。
本記事では、相続税の基礎から計算方法まで、理解しやすく解説します。これを参考に、相続税の仕組みをしっかりと理解し、準備を進めましょう。
相続税とは
相続税は、故人の遺産を相続した人が支払う税金のことをいいます。相続において、親族間で財産の移転を伴いますが、その際、税務署に対して所定の手続きを行い、相続した遺産の金額に応じて税金を納めなければなりません。
具体的は、「相続」「遺贈」「死因贈与」により財産を受け取った場合にかかるもので、故人との関係性や承継方法によっては、贈与税がかかるケースもあります。
【関連記事】遺贈の種類、必要な手続、注意点を解説
【関連記事】死因贈与に必要な手続、メリットと注意点を解説
相続税の課税対象となる遺産総額の計算方法
相続税を算出する際、基礎となるのは「課税遺産総額」であり、以下の方法で算出することができます。
- 遺産総額の価額と、相続時精算課税の適用を受けた財産の価額を合計
- 1から債務、葬儀費用、非課税財産を差し引く
- 遺産額に加算対象となる暦年課税に係る贈与財産の価額を加算し、正味遺産額を算出
- 3から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出
1.遺産の課税対象となる財産
遺産に含まれるものは、ほとんどが相続税の課税対象となりますが、以下に例を挙げます。
- 現金、預貯金
- 土地、建物
- 株式(上場、非上場を問わない)
- 投資信託
- 公社債
- 生命保険の死亡保険金
- 死亡退職金
- 事業用財産
- 貸付金や未収金
- 自動車やバイク
- 金地金
- 書画骨董
- 電話加入権
- ゴルフ会員権
- 家庭用財産
- 海外資産
- 亡くなる前3年以内の贈与 など
1.1. 相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、贈与税の特例の一つで、故人が生前に贈与した財産について、相続税の申告時にいっしょに精算する仕組みをいいます。そのため、贈与時には一定額まで非課税となりますが、相続財産に含まれることから相続税が高くなるおそれがあります。
【関連記事】相続時精算課税制度のポイント、活用例、注意点を解説
2. 相続税の課税対象とならない財産
以下の財産については、相続税の課税対象とはなりません。
- 墓所、仏壇、祭具など
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 生命保険金の控除額まで
(500万円×法定相続人の数) - 死亡退職金の控除額まで
(500万円×法定相続人の数)
【関連記事】お墓の相続に必要な手続き、注意点を解説
3.遺産額に加算対象となる暦年課税に係る贈与財産とは
遺産額に加算対象となる暦年課税に係る贈与財産とは、相続時精算課税制度を選択していない場合に、加算対象期間内に贈与された財産について課税対象となります。
【関連記事】生前贈与の非課税枠、注意点を解説
3.1. 加算対象期間
加算対象期間とは、以下の通りです。
| 故人の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| ~令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内 (死亡日から遡って3年前の日から死亡日までの間) |
| 令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡日までの間 |
| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内 (死亡日から遡って7年前の日から死亡日までの間) |
加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、相続税の計算上引かれます。
3.2. 加算される贈与財産の範囲
加算される贈与財産の範囲について、故人から生前に暦年課税に係る贈与により取得した財産のうち、加算対象期間内に贈与されたものです。加算対象期間内に贈与された場合には、贈与税がかかったかどうかに関わらず、加算されます。
そのため、暦年贈与の基礎控除額110万円以下の贈与財産や、死亡した年に贈与された財産まで加算されることとなります。
3.3. 加算しない贈与財産の範囲
いっぽう、以下に該当する財産については、故人から生前に贈与されていても加算する必要はありません。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けている、または受けようとする財産のうち、その控除額に相当する金額
- 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
- 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
- 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
3.4.対象者
暦年課税に係る贈与財産の加算対象となるのは、相続等により財産を取得した人で、故人から加算対象期間内に暦年課税に係る贈与により財産を取得した人です。
3.5. 計算方法
相続税の課税価格に加算する金額は、贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して算出します。
課税遺産総額=遺産総額+贈与財産額ー非課税財産+債務+葬儀費用ー基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」について、相続放棄した人がいた場合でも、その放棄はなかったものとしてカウントします。また、法定相続人の中に実子と養子がいる場合、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。一方、実施がいない場合には、養子のうち2人までを法定相続人に含めることができます。
ただし、特別養子縁組の場合は実子扱いとなりますので、人数に制限はありません。
※相続開始の日が令和9年1月2日以降の場合、加算対象期間内に取得した財産のうち、相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その贈与時の価額合計額から総額100万円まで相続税非課税となります。
①相続税額から控除する贈与税額
加算対象となる贈与財産ついて支払った贈与税がある場合、その相続税額から贈与税額に相当する金額を控除します。控除する贈与税額は、贈与のあった年ごとに以下のとおり計算します。
イ.故人から暦年課税に係る贈与により特例贈与財産を取得した場合
その年分の特例贈与財産に係る贈与税額×その年分の特例贈与財産の合計額÷その年分の特例贈与財産の合計額のうち、相続税の課税価格に加算された特例贈与財産の価額
ロ.故人から暦年課税に係る贈与により一般贈与財産を取得した場合
その年分の一般贈与財産に係る贈与税額×その年分の一般贈与財産の合計額÷その年分の一般贈与財産の合計額のうち、相続税の課税価格に加算された一般贈与財産の価額
相続税の計算方法
課税遺産総額がわかったら、以下の方法で相続税を算出します。
- 課税遺産総額を法定相続割合で分割
- 各相続人の法定相続分に応じた取得金額を算出
- 相続税を算出
- 各相続人の取得割合に応じて按分し、各自の負担額を算出
- 各相続人が利用できる控除を適用
1.課税遺産総額の算出
課税遺産総額は、「遺産総額+贈与財産額ー(非課税財産+債務+葬儀費用)ー基礎控除額」にて算出します。
2.各相続人の課税遺産額を算出
各相続人の課税価格の合計は、課税価格の合計額と等しくなります。
3.各相続人の法定相続分に応じた取得金額
各相続人の取得金額は、
法定相続割合とは
法定相続割合とは、法律で定められた各相続人の相続割合をいい、以下の通りです。
| 故人との関係 | 配偶者 | 子 (孫) | 父母 (祖父母) | 兄弟姉妹 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1 | ー | ー | ー |
| 子がいる場合 | 2分の1 | 2分の1 | ー | ー |
| 父母がいる場合 | 3分の2 | ー | 3分の1 | ー |
| 兄弟姉妹がいる場合 | 4分の3 | ー | ー | 4分の1 |
課税遺産額に法定相続分をかけた後、各相続人に適用される控除額を差し引いて、相続税額を計算します。
各相続人の法定相続分に応じた取得金額=課税遺産総額×法定相続分
相続税の課税率は、下表のとおりです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
上表を基に、各相続人の法定相続分に応じた取得金額に相続税率をかけ、相続税の総額の基となる金額を算出します。
算出税額=各相続人の法定相続分に応じた取得金額×税率ー控除額
4.全体の相続税額を算出
各相続人ごとの算出税額を合計し、相続税の総額を計算します。
各相続人ごとの算出税額の合計額=相続税の総額
5.各相続人の実際の相続税額を算出
相続人が納めるべき実際の相続税額を算出するには、相続税の総額を、財産を取得した各相続人の課税価格に応じて割り振ります。
各相続人の課税遺産額=相続税の総額×各相続人の課税価格÷課税額の合計
6.適用できる税額控除をそれぞれ適用する
各相続人の課税遺産額から、相続人に適用される各種税額控除額を差し引いた残りが、実際の納付税額となります。
ただし、財産を取得した人が故人の配偶者、子、父母以外の場合、税額控除を差し引く前の相続税額に2割を加算した金額から、税額控除額を差し引くこととなります。
- 暦年課税分の贈与税額控除
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
①暦年課税分の贈与税額控除
暦年課税分の贈与税額控除とは、故人から生前贈与を受けた際に贈与税を納付していた場合、その贈与税分を相続税から控除できる制度をいいます。これは、贈与税と相続税の二重課税回避のために設けられたルールです。
贈与税額控除額=贈与を受けたその年分の贈与税の金額×贈与を受けたその年分の贈与財産の合計額÷相続税の計算時に足し戻した贈与財産の価額
②配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、故人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額について、以下のうちどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからない制度です。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
この制度は、配偶者が実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに分割されていない財産については、税額軽減の対象とならない点に注意しましょう。
- 法律上の配偶者であること
- 申告期限(相続開始から10か月)までに遺産分割協議が確定していること
- 相続税の申告書または更生請求書に添付書類を添えて提出すること
ただし、相続税の申告期限までに遺産分割が調わないなどの理由から分割できない場合、相続税の申告書、または更生の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、実際に申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象となります。
未成年者控除
未成年者控除とは、相続人の中に未成年者がいる場合に、その未成年者の相続税額から一定額を控除する制度をいいます。
①未成年者控除の適用を受けられる人の条件
相続税の未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
- 相続や遺贈で財産を取得したときに、日本国内に住所がある人
- 相続や遺贈で財産を取得したときに18歳未満の人
- 相続や遺贈で財産を取得した法定相続人
上記1について、相続や遺贈による財産の取得時に日本国内に住所がない場合でも、以下のいずれかに当てはまる場合には未成年者控除を受けることができます。
- 日本国籍があり、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所があった人
- 日本国籍があり、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所をもったことがない人
- 日本国籍がない人
※故人が外国人、非居住または非居住外国人の場合は除く
※未成年者とは
ここでいう「未成年者」とは、2022年3月31日以前の相続、または遺贈については20歳未満ですが、2022年4月1日以降に生じた相続、または遺贈については18歳未満をいいます。
②未成年者控除の額
未成年者控除の額は、未成年者が満18歳になるまでの年数1年について10万円で計算した額です。
未成年者控除の額=10万円×(20歳-相続開始時の年齢)
年数の計算にあたり、1年未満の期間については切り上げ「1年」として計算することができます。
万が一、未成年者控除額が未成年者の相続税額より高くなり、控除額の全額が引き切れない場合には、引き切れない金額をその未成年者の扶養義務者の相続税から差し引くことができます。
扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
【関連リンク】No.4164 未成年者の税額控除(国税庁)
障害者控除
相続税の障碍者控除とは、相続人が85歳未満の障碍者の場合に、その障害者が満85歳になるまでの1年について10万円を控除できる制度です。
①障害者控除の適用が受けられる人
障害者控除が受けられるのは、以下のすべてを満たす人です。
- 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
- 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人
- 相続や遺贈で財産を取得した法定相続人
②障害者控除の額
障害者控除の額は、一般障害者の場合は満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額、特別障害者の場合は1年につき20万円です。
- 障害者控除:10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)
年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。また、障害者控除額が相続税額より大きく、控除額の全額を引ききれない場合には、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
【関連リンク】No.4167 障害者の税額控除(国税庁)
相次相続控除
相次相続控除とは、今回の相続開始前10年以内に故人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与により財産を取得し、相続税が課されていた場合に、その故人から相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除する制度です。
①相次相続控除が受けられる人
相次相続控除が受けられるのは、以下のすべてに当てはまる人です。
- 故人の相続人
- その相続の開始前10年以内に開始した相続により個人が財産を取得していること
- その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、故人に対し相続税が課税されたこと
②相次相続控除の額
相次相続控除は、前回の相続に置いた課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除するものです。
各相続人の相次相続控除額は、以下の算式により計算します。
各相続人の掃除相続控除額=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)
A:今回の故人が前の相続の際に課せられた相続税額
B:今回の故人が前の相続の際に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税の適用を受ける財産の額ー債務および葬式費用の金額)
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満は切り捨て)
※2024年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産について、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額となります。
【関連リンク】No.4168 掃除相続控除(国税庁)
外国税額控除
相続税の外国税額控除とは、海外で支払った相続税額を上限として、日本で支払う相続税のうち海外財産が占める割合分の相続税を控除できる制度です。
①外国税額控除の適用を受けられる人
相続税の外国税額控除の適用を受けられるのは、以下のいずれも満たす人です。
- 相続、また遺贈により日本国外の財産を相続した人
- 日本国外の財産について、その外国において相続税に相当する税が課税された人
相続人が外国に居住している場合、次のいずれかに該当する人が相続税の納税義務者となります。
| 無制限納税義務者 | 居住無制限納税義務者 | 相続または遺贈により財産を取得した次に掲げる人のうち、その財産を取得したときにおいて日本国内に住所がある人 イ.一時居住者でない個人 ロ.一時居住者である個人 |
| 非居住無制限納税義務者 | 相続または遺贈により財産を取得した次に掲げる人のうち、その財産を取得したときにおいて日本国内に住所がない人 イ.日本国籍を持つ個人で、①遺産の相続が始まる10年前までに日本に住所があった人、または②遺産の相続が始まる10年前からずっと日本に住所がない人(ただし、相続される財産の持ち主が外国籍である場合を除く) ロ.日本国籍を持たない個人(ただし、相続される財産の持ち主が外国籍である場合を除く) | |
| 制限納税義務者 | 相続または遺贈により財産を取得した個人で、その財産を取得した時において、(1)日本国内に住所がある人()居住無制限納税義務者を除く、または(2)日本国内に住所がない人(非居住無制限納税義務者を除く) | |
| 特定納税義務者 贈与により相続時精算課税適用財産を取得した個人 | イ.無制限納税義務者の場合 | 国内財産、国外財産および相続時精算課税適用財産 |
| ロ.制限納税義務者の場合 | 国内財産および相続時精算課税適用財産 | |
| ハ.特定納税義務者の場合 | 相続時精算課税適用財産 | |
②外国税額控除の額
相続税の外国税額控除は、以下のいずれか少ない金額です。
- 外国で支払った相続税に相当する税
- 相続税の額×海外にある財産の額÷相続人の相続財産の額
【関連リンク】No.4152 相続税の計算
おわりに
相続税は、その計算方法や控除額が複雑ですが、正しく理解し適切に申告することが大切です。この記事でご紹介した内容をもとに、相続税の基本を把握し、実際に相続が発生した際の手続きをスムーズに進められるように準備をしましょう。もしも不安な点があれば、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。